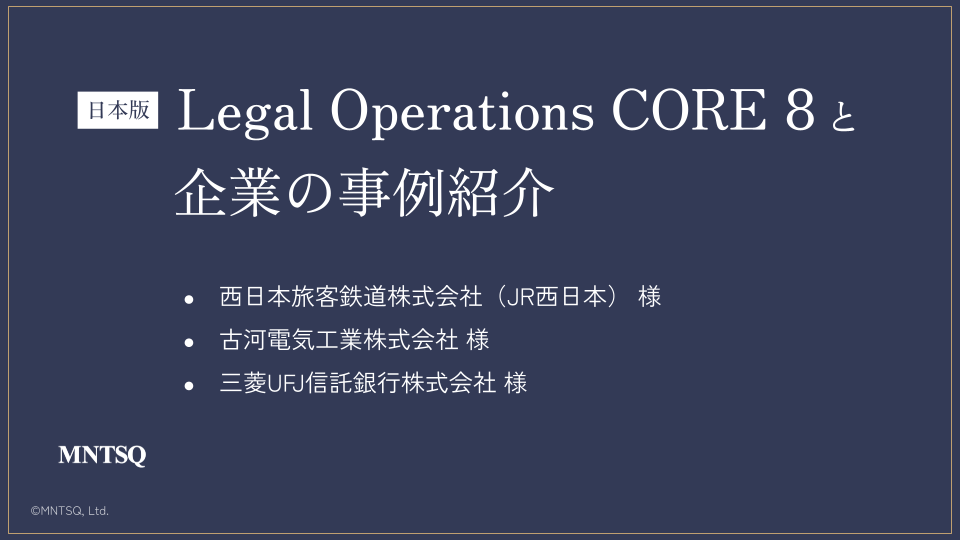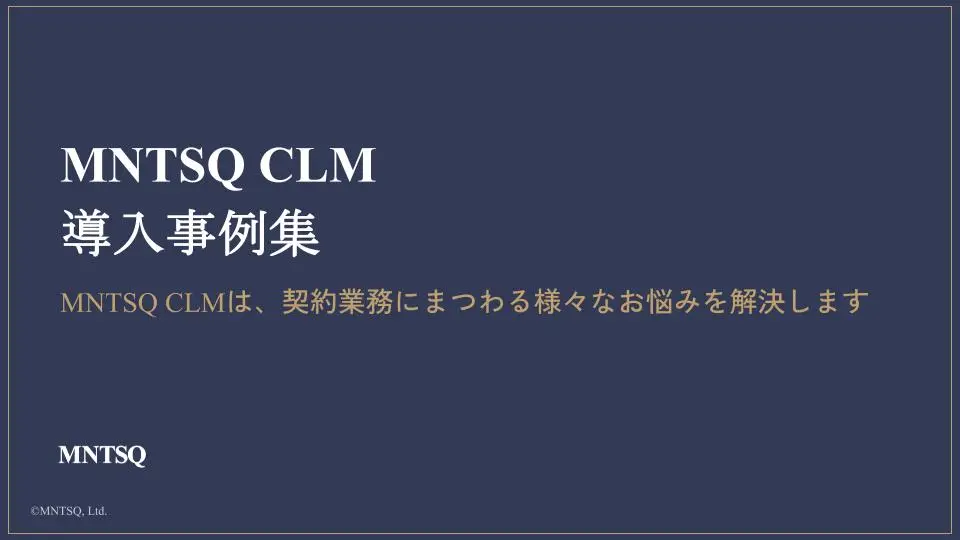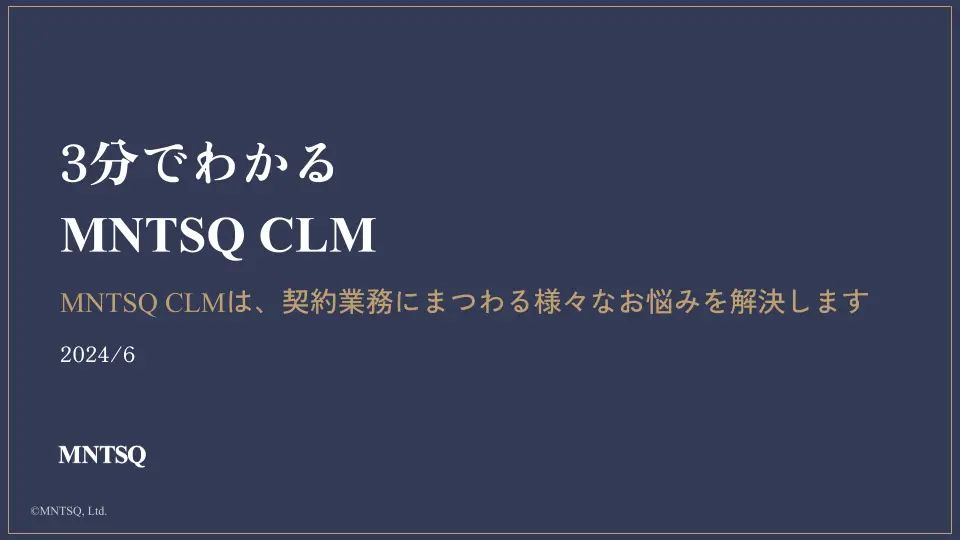国内業務に加え、海外部門との連携を強化するフェーズに
まず、日置電機様の法務部門の体制について教えていただけますか。

満木:
これまでは「知財法務室」という名称で、取締役直属の部署として独立していましたが、昨年から総務本部に組み込まれ、「知財法務部」という組織になりました。
総務本部に組み込まれた一番の目的は、グループ一体での経営方針をとるためです。現在は売上の海外比率6割から7割を目指すステージにあり、海外の法務部門を持たない子会社との連携強化にも取り組んでいます。
現在は11名が在籍しており、法務では専任者が1名、その他兼務の形で3名がその役割を担っています。
契約書のレビューが主要な業務で、顧問弁護士とのやり取りも含め、ビジネスに関する法務の問い合わせ窓口となっています。
では、現在は国内外の全ての法務関連業務を皆様で対応されているのでしょうか。
満木:
まだ海外連携をスタートしたばかりなので、海外案件すべてを受けられているわけではなく、これから徐々に私たちが関与する件数を増やしていく段階です。海外子会社に関しては契約書関連の業務がメインになるので、まずはそこから押さえていきます。ある程度大きな案件は各国の拠点が現地の弁護士と連携して対応してもらっていますが、今後はそちらもカバーできるよう対応範囲を広げていきたいですね。
海外の場合、まだ立ち上げフェーズの拠点も多く、さまざまな契約の締結が必要なケースがよくあります。ただ、現地ではビジネスの推進を優先する傾向が強く、必ずしも適切にレビューした上で契約締結できているわけではありません。そのような案件に関しても私たちがしっかりと関わっていくべきだと考えています。
社内システムを導入したものの、属人化の課題は解消できなかった
MNTSQ導入前はどのような課題を抱えていましたか。

関谷:
私はもともと技術部門に所属していたのですが、満木が考える知財法務部の業務変革構想を実行するために知財法務部へ異動しました。業務変革を実行するためには、プロセスの理解が必須だと考えていましたので、法務知識はほとんどありませんでしたが実務に携わるようになりました。その中で、ナレッジマネジメントに関する課題に気付きました。
例えば、契約書のレビューや作成業務は、似たような過去の契約書を探して真似をすればある程度形にはなります。ただ、その過去の契約がどのような経緯でできたのか、どのような背景があったのか、メールベースでやり取りされていた情報は残っていないので汲み取れず、審査の基準もわからない状態でした。もちろん法務部のメンバーから教えてもらえれば理解はできるのですが、このまま属人的な仕組みを継続するのはリスクがあると感じました。

金井:
そのような属人化した状態を改善するために、MNTSQ導入の以前から、契約の審査・作成依頼等の窓口を一本化し、各案件の情報を法務部内で共有できるシステムを導入してはいました。他にも、AIレビューツールや電子契約システムを導入したりと、プロセスごと、課題ごとにデジタル化して手を打ってきたつもりでした。
しかし、審査基準が個人でばらつきがあること、業務プロセスを部分的にデジタル化してもプロセス間のつなぎは結局人力になってしまうことや、多くのデータや紙での過去契約から法務担当者が必要な契約書を探し出すような状況は解消できていませんでした。
満木:
金井が推進したシステムに関して、プロセスはほぼ完成していましたが、社内での利用が徹底できませんでした。法務の5割はシステム内でやり取りが残せる仕組みになっていたものの、残りの5割はシステムを介さず、これまで同様にメールで相談が来てしまうのです。
メールで来たものはメールで返すしかなく、メールのファイルは社内のデータベースに蓄積されても、情報はあっても活用はできない状態でした。やはり「ナレッジマネジメント用のツール」が必要だと考えました。
MNTSQのビジョンに共感、営業担当者の対応も信頼できた
MNTSQ導入に至った経緯を教えていただけますか。
満木:
AIの進化に伴い法務DXの期待感も高まり、様々なリーガルテック企業の情報を収集している中で、MNTSQのウェビナーに参加し、板谷代表のプレゼンを聞いたことが問い合わせのきっかけとなりました。私が漠然とイメージしていた法務の理想像を、「私たちはこのような世界を目指しています」と明確に言語化されていたのがとても印象的でした。MNTSQを導入することで、私たち法務部が目指す姿に近づけるのではないかと思いました。
金井:
私も満木と一緒に情報収集している中で、課題だった、分断された業務プロセスを繋げるためにCLMという手法が有効だと知りました。複数のデジタルツールを導入し、それらを連携させるための運用を考えるのではなく、業務プロセスを一気通貫できるCLMで法務業務を完結させたいと考えました。そこで何社かお話を聞き、そんな中でMNTSQの板谷さんからも、目指す世界観のお話を伺うことができました。自社のCLMのイメージが持てたこと、さらに営業担当者の対応も素晴らしかったことから、かなり早い段階で導入の検討に入りました。
満木:
営業担当者の方との初めてのミーティングの場でいくつか質問したのですが、宿題で持ち帰る部分がなく、その場で全て丁寧に回答いただいたのには驚きました。すぐにHIOKIの現状のシステム構造を可視化し、MNTSQ導入後の運用イメージも作成いただきました。
また、今回のツール導入にあたり、私が経営陣に宣言していたぐらい重視していたのが「脱メール」です。この「脱メール」に関しても、どのように実現していくべきか、MNTSQ導入前の段階だとイメージしづらかったのですが、私たちの迷いや疑問を都度汲み取って解消いただけたため、安心してシステム構想を進めることができました。
関谷:
複雑な契約レビューのプロセスを、MNTSQでシンプルに実装できるようなご提案もいただけました。MNTSQの構造を理解すること自体が、契約業務のプロセス自体の見直しに繋がったと思います。
検討段階で、MNTSQでできること/できないことを、明確にわかりやすくお話しいただけた点も良かったです。
満木:
導入後、窓口が営業担当からカスタマーサクセス担当の方に変更になった際、営業担当の方とこれまでと同じレベル感で対応いただけるのか、正直なところ不安がありました。
しかし、実際引き継いだ後、カスタマーサクセス担当の方にも、導入計画や進捗管理など、本当に丁寧にリード・伴走いただけました。関谷がシステムのプロセスを細かくチェックしていましたが、それに対してサポートにとどまらないご提案をいただいたため、どんどん導入後の内容などが明確になり、安心して任せることができました。
関谷:
打ち合わせ資料も議事録も送っていただいたので、その資料をベースに導入計画のタスクや設定項目を検討するサイクルを回すことができ、とても助かりました。丁寧かつ先回りしたフォローや支援があったからこそ、スケジュール通りに導入できたのだと思います。
導入後すぐに脱メールを実現。期待以上の効果を実感
実際に導入されて、現状はいかがでしょうか。
満木:
一番実現したかった「脱メール」は期待以上に、完全に解決しました。たまにメールで来てしまうものもありますが、途中からすべてMNTSQに入れ直せば情報はMNTSQに蓄積されます。法務相談については、契約に限定されずすべてMNTSQに集約できました。海外拠点からもアクセスできるようになり、想定された課題は全てクリアできています。
関谷:
メールで依頼が来た相談もすべてMNTSQに集約することで、曖昧だった法務部への依頼や相談の全体件数が明確に可視化できた点も良かったですね。
金井:
契約書の検索や閲覧で言えば、過去の契約は紙のものもすべてデータ化したうえでMNTSQに集約し、まとめてMNTSQで検索・閲覧できる状態にしたかったんです。バインダーから書面を探したり、フォルダやデータを探し出すようなことはせず、ストレスなく欲しい情報を検索できる状態にしたかったのですが、目指していた状態がほぼ実現できています。
MNTSQ導入前に既存のシステムを入れてみたものの、やっぱりメールに戻ってしまったっていうところのお話があったと思います。今回は事業部側の皆様もMNTSQを利用いただけているということでしょうか。
金井:
はい、海外部門も含め全社で利用が広がっていますね。MNTSQの、一度ログインすればそのまま直感的に使える操作性の良さがあったからこそだと思います。従前の社内システムでは、システムそのものの使い方に対する質問が非常に多かったのですが、MNTSQの場合はメールに返信すれば自動的にMNTSQに蓄積される仕組みであることもあり、事業部側の手間を増やさずにスムーズに導入できたと思います。
「HIOKIらしさ」のある契約書の標準を作っていきたい
法務部としての今後の展望についてお聞かせください。
金井:
優先して取り組みたいと考えているのは、事業部側とのコミュニケーションの促進ですね。現状、弊社の事業部側で契約書の内容を理解しきるにはなかなか難しい部分もありますが、本来は、事業部の担当者自身が、今回の契約で何を実現したいのか、どのような要件を検討すべきなのかを理解できている状態が健全だと思います。そこでまずは、法務部以外の社員でも理解しやすいよう契約書の雛形をできるだけシンプルに、わかりやすい内容に整備していくこと、そして事業部側の理解を促進できるような教育・研修の機会も創出したいと考えています。
満木:
加えて、「HIOKIらしさ」が反映された契約書の雛形を作りたいです。企業法務として法令遵守を大前提に、HIOKIの取引拡大に貢献できる契約プロセスの実現を目指し、経営計画の達成とリスク管理が両立できるような契約書が理想です。そのような契約書の正解は世の中にはないので、私たちとお客様で一緒に作っていきたいと考えています。
日置電機株式会社の皆様、お忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。