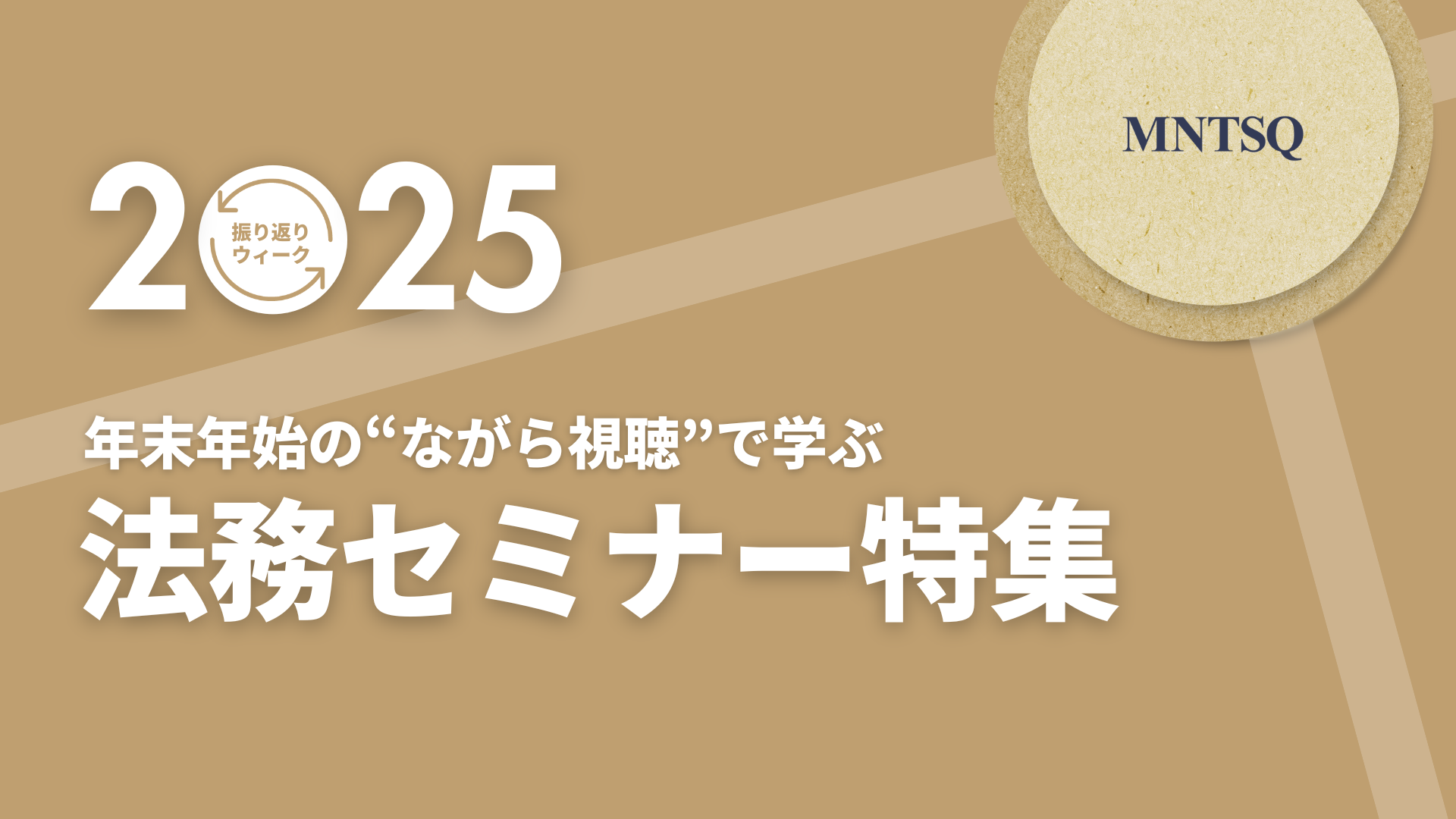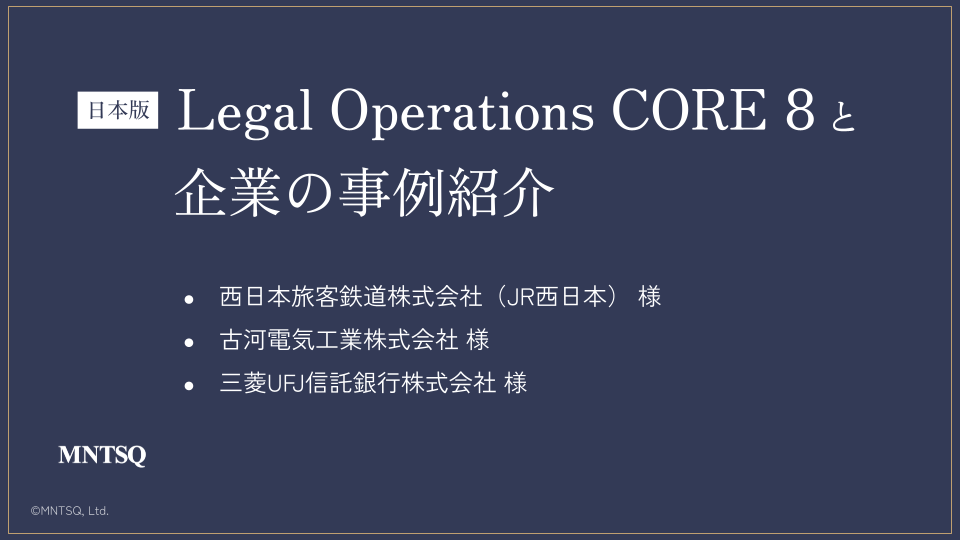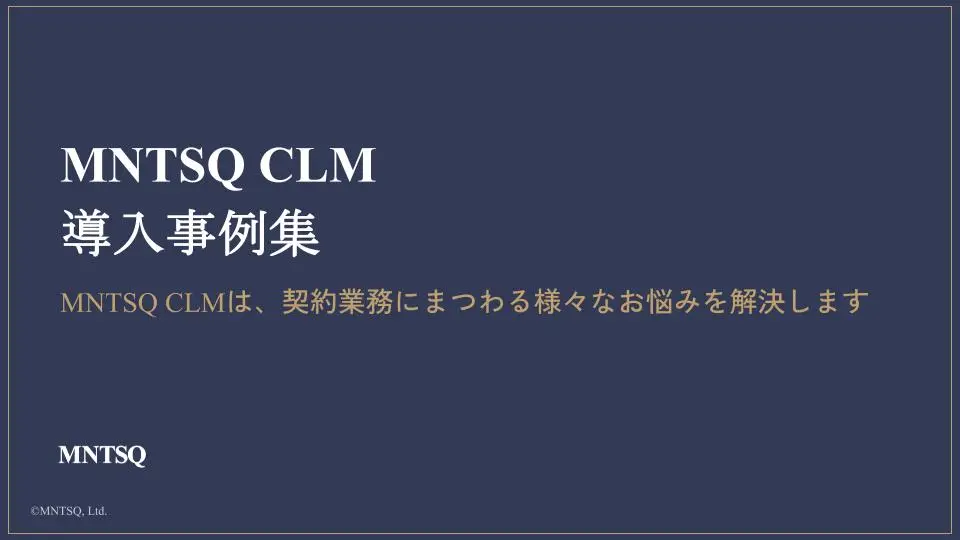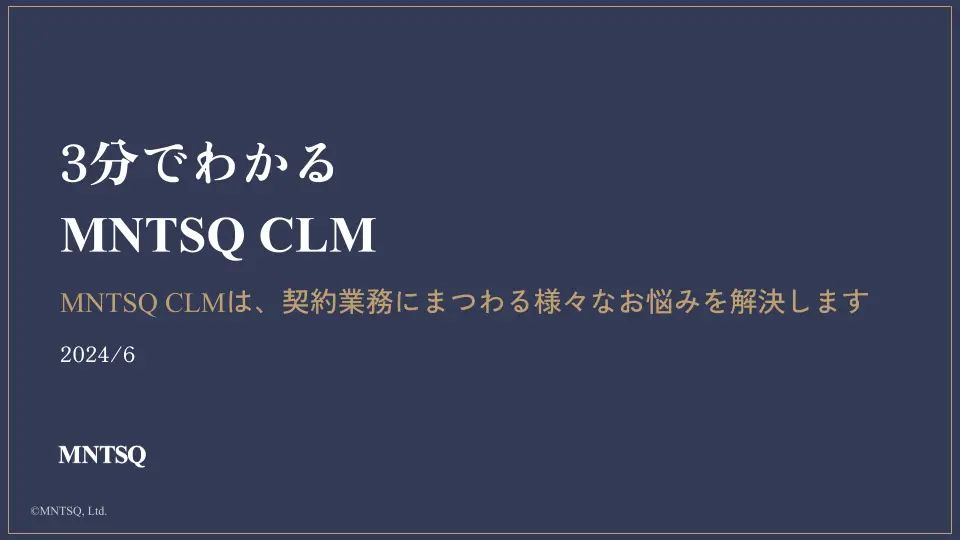<参加者>
法務コンプライアンス部 法務第一課長 團 章一郎様
法務コンプライアンス部 法務第一課 深瀧 百羽様
法務コンプライアンス部 法務第一課 白水 花野様
MNTSQ カスタマーサクセス担当 藤井のど佳
※以下、敬称略
※2025年10月時点の役職です
法務コンプライアンス部の閉塞感を打破すべくDX推進を決意
MNTSQ 藤井:
まずは、兼松さんがどのような事業を推進されているのか、ご紹介いただけますか。

深瀧:
当社はICTソリューション、電子・デバイス、食料、鉄鋼・素材・プラント、車両・航空の5つの領域でビジネスを展開している商社です。
ICT分野では、ITインフラ構築やセキュリティ対策、情報システムのコンサルから運用・保守までをワンストップでサポート。電子・デバイス分野では、データやAI、素材から装置まで独自のバリューチェーンを構築し、付加価値を創出しています。食料分野は「食の安全・安心」を掲げ、一貫供給体制による高付加価値な食材や加工品の安定供給が強みです。
鉄鋼・素材・プラント分野では、鉄鋼製品やエネルギー、化学品、木材、映像関連まで専門性高く幅広く対応。車両・航空分野では、自動車部品や完成車、航空機や宇宙・防衛分野に至るまで、豊富な知識と情報を活かしたグローバルな事業展開を行っています。こういった背景から、相談事項も多岐にわたり、法務コンプライアンス部には各事業への理解と柔軟な対応が求められます。
MNTSQ 藤井:
ありがとうございます。皆さまがDXをスタートさせたきっかけを伺ってもよろしいでしょうか。当時の現場で感じておられた課題をお聞かせください。
團:
私は兼松に入社して以来、20年ほど経ちますが、法務コンプライアンス部を中心にリスクマネジメント部、主計部に所属し、2018年からアメリカに駐在していました。2022年に私が駐在から戻ったとき、当時の法務コンプライアンス部にいた中堅メンバーから「リーガルテックの導入によるDXを推進したいと考えていたものの、なかなか進められていない」と相談されたのが1つのきっかけでした。
ただ、リーガルテックの有用性は感じたものの、即座に導入を進めたわけではなく、先ずは、組織の課題やメンバーの持つ課題感を確認して、そのうえで、各課題に対する打ち手の1つとして、リーガルテックの導入を適宜行っていきました。
当時のメンバーとのコミュニケーションや実際の執務を経て、法務コンプライアンス部は、業務の不効率、知識や経験の属人化に陥っており、結果として、事務作業や情報収集に時間と労力が割かれ、本質的な作業である情報分析や分析結果に基づくアウトプット(契約やアドバイス)の準備や提示に集中できていない、という課題を認識しました。そのような課題があるため、各メンバーが質の高いアウトプットの提供を目指すものの実現できず、結果としてプレゼンスが発揮できない状況に陥っており、全体に閉塞感が漂っている状況でした。
私のチームは若手メンバーで構成されているため、特に、事務的な作業の割り当てが多く、また、知識や経験がシニアメンバーに比して不足するため、この傾向がより強かったと思いますが、一方で、課題解決に対する意欲も強く、MNTSQ導入をはじめとするDXを強烈に推進してくれました。
MNTSQ 藤井:
なるほど、あくまで課題ファーストで取り組まれたのですね。具体的には、お話いただいた課題解決のために、どのような取り組みをなさったのですか。
團:
課題を1つ1つ見ていく過程で、属人的でアナログな業務プロセスや人材育成プロセス、また、社内外交流の不足による客観的な視点の欠如が主要な原因だと考え、①情報や経験を共有する仕組み作り、②平準化された人材育成システム構築、③外部企業との交流の3つが解決するために必要だと考えました。
特に、①情報や経験を共有する仕組み作り が重要だと考え、まずは、ある程度各メンバーが何をやっているのかを可視化できるようBox(クラウドストレージサービス)を用いた情報共有の仕組み作り、自分の過去の経験の共有、法務チームで勉強会の開催といったところから始めました。
ただ、いずれの取り組みも、課題解決の方向性としては合っていると思いますが、アナログな対応では限界があるため、よりしっかりと仕組み化されたものの導入が必要だと考え、リーガルテックの導入を進めました。
MNTSQ 藤井:
團さんが戻ってこられる前から、法務コンプライアンス部のそれらの課題を解決しようという動き自体はあったのでしょうか。
深瀧:
先輩方が動こうとはしていたのですが、時間や費用の制約が課題となり進められていませんでした。
私は團さんが米国から戻る半年前に新卒で入社して法務コンプライアンス部に配属されたのですが、業務遂行の方法に関しては、本当に何もわからない状態で。過去の資料を頑張って探し出したりとか、他のメンバーにも色々聞いて、合ってるかわからないけどとにかくやってみて何とかできた、というやり方をせざるを得ませんでした。
ただ、自分の進め方や判断が問題ないのかどうかの判断もつかず、業務を進める上での不便さや閉塞感は実感していましたね。その中で團さんが米国駐在から戻って話を聞いて、自分が日ごろ悩んでいたことは、さっき團さんが言ったような属人化や非効率なワークフローといった課題に起因する部分もあると感じました。自分や今後法務に配属される若手のために、本質的な仕事に集中できる環境を整備していくべきだと思い、團さんや他メンバーと一緒にリーガルテック導入を中心としたDXを推進することにしました。
停滞していたところからDX推進の承諾を得られた理由

MNTSQ 藤井:
團さんが戻られてから改めてもう一度DXを進められた形になると思うのですが、社内コミュニケーションはかなり大変だったのではないかと思います。実際どのように進められたのでしょうか。
深瀧:
仰る通り、ただ「DXをやらせてください」と言っても難しいだろうと思いました。なので、チームメンバーと協力してas isの課題と、to beの理想の姿、それを実現するための打ち手という形で十分に整理し、上層部および関係部署への説得材料を丁寧に揃えた上で、DXを含めた改善施策の提案を行いました。
具体的には、まず、現状の属人的かつアナログなフローによって起きている課題を整理し、それらの課題が解決された理想的な状態を描きました。理想像は、世の中で流通している法務関連の情報と、自社のナレッジ双方に簡単にアクセスできる状態にして、情報探しという作業に時間を取られるのではなく、分析業務など私たちが価値を発揮すべき業務に集中し、アウトプット品質の平準化と向上を同時に実現できること。これを実現するためにMNTSQをはじめリーガルテックの導入、つまり、DXが必要だとプレゼンしたところ、上層部および関係部署からスムーズに承認していただけました。
MNTSQ藤井:
課題を整理し、解決策と理想の姿を明確に伝えることが承認を得るために重要なのですね。
深瀧:
そう思います。
MNTSQを導入する際も、先ほど述べたようなto beを実現するために最適なリーガルテックとして提案したところ、上層部および関係部署から同意をもらえました。提案する自分自身としても、明確な課題感から出発しているので、一貫した説明をできたと思います。
團:
あと、最初にお話しした通り、常に課題をベースとして、その解決策の1つとしてリーガルテックを検討する方式としたため、社内承認の取得とリーガルテックの導入を1つ1つ進めました。
具体的には、まずは、関係者が部内に限定される法律情報のリサーチツールを導入し、リーガルテック導入による効果を実感し、感じていた課題の改善の兆候が見えてきたら、徐々に適用範囲や導入ツールを拡大していきました。それまで法務コンプライアンス部として、DX推進ができていなかったこともあり、スモールスタートで、1つ1つ着実に導入するカタチが適していたと思います。
MNTSQ 藤井:
上層部および関係部署の説得は多くの企業が最初につまずくところだなと思います。DXには一定の予算や工数が発生しますし、自分の仕事だけやっててと突き返される例もよく聞きます。もし他社にアドバイスされるとしたらどのようなポイントを伝えますか?
白水:
通常業務もある中で、DX推進に注力することは、ある程度の負荷はかかりますが、正直、勢いというか担当者の熱意が重要だと思います。熱意は課題感の強さに比例しますよね。その課題意識を持って、打ち手と理想像が見えているのであれば、説得材料を集めて進めていくしかないかなと。
MNTSQ 藤井:
本当にその通りだと思います。旗振り役の團さんだけでなく、推進メンバーである白水さんや深瀧さんも同じぐらい熱量を持って取り組める状態に持っていくのは、組織としてはなかなか難しいと思っていて。やらされ仕事にならず、全員の目線が合った状態で、目的を見失うことなく推進できた要因はなんでしょうか。
白水:
私自身、法務関連の知識や経験がないところから法務コンプライアンス部に配属され、抵抗感がある中、法務業務に必要な能力を高めるための適切な情報も少なく、正解もわからない中でなんとか業務をこなさなければいけない状況が嫌でした。真っ暗ななかで懐中電灯を頼りに、全体像が見えないなかで仕事している感覚を持っていたため、その状況をなんとか解消したいという気持ちが原動力になっていたと思います。
また、常にDX推進メンバーで目線合わせの打ち合わせを行っており、目指すべきところと課題感については共通のものを持っていたため、目的を見失わず進めることができたと思います。
深瀧:
私も、半年働いて、もっと本質的な仕事をしたいという感覚はありつつ言語化ができていませんでした。その中で團さんのお話を聞いて、まさにこれがやるべきことだと気付きました。実際にチームでDXを推進して、MNTSQのようなツールの導入ではなく、既存ツールを用いた小さな工夫のような取り組みもたくさんあるのですが、いろいろトライしていくうちに少しずつ実になって、成功体験を着実に積み重ねていけました。
本当に大変ではありましたが、前に進んでいる実感があると仕事も楽しくなってくるので、ここまでやってこれたと思います。

DX予算獲得の交渉では、法務コンプライアンス部が抱える課題を根気強く伝え続けた
MNTSQ 藤井:
ここからは、予算について伺えればと思います。DX予算は会社と調整しながら進めていかなければいけないので、ここで苦戦している企業は多いと思います。皆さんの場合、どのように予算を通されたのか教えていただけますか。
深瀧:
法務コンプライアンス部には、そもそもリーガルテック導入に関しては決まった予算がなかったんですよね。予算がないからこそ金額にとらわれず、自分たちの課題を解決できるものであれば金額に拘わらず導入しましょうという流れで進められました。ただ、実際に承認されるまでかなりの時間と労力がかかりました。
どの企業でも同じだと思いますが、昨今はコストカットの意識が強く、とりわけバックオフィス部門の予算純増は認められないというスタンスではありました。
私たちがMNTSQ導入のための予算申請をした際は、DXの構想、ツール選定、予算承認といったステップごとに社内のDX推進にかかる会議体に諮り、また、関係部署の担当者に対して地道に説明して、1人ずつ理解し協力してくれる方を増やし、承認に至りました。
ただ、これまでずっとお伝えしている通り、「人件費などのコストがカットできます」という文脈での説明は一切行わず、「もっと本質的な業務に充てる時間を増やし、より良いアウトプットのためにナレッジマネジメントするべきであり、そのためにMNTSQの導入が必要」という課題と打ち手という観点からの説明を一貫しました。

白水:
やはり、効率化によるコストカットをアピールした方が予算は取りやすいと思います。これを入れることで、法務コンプライアンス部に新しく人材を1人取るべきところが取らなくても済みますよとか。でも、リーガルテック導入の目的はそこではなく、効率化したうえでアウトプットの質を上げることや、手を付けられていない業務へ取り組むことだと考えています。
実際、今は非効率な業務が減ってきているのですが、それによって人を減らすのではなく、その分新しい業務に取り組んでいます。直近でいうと、これまで取り組めていなかった「グループ会社とのコミュニケーション」を行っています。グループ会社に訪問し、各社の法務体制について話を聞いた上で、不安に感じている点や改善すべき点を協議する機会を設けているのですが、その文脈の中の一つの施策として、グループ全体で、MNTSQを使うことで、当社の法務コンプライアンス部と連携を強めていきましょう、リーガルリスクを適切に管理するために、グループ間での情報交換もしましょうという形で提案しています。
MNTSQをフックにグループ会社との連携が今までと比較して容易になると考えているため、MNTSQをきっかけとして交流を増やすことができています。業務効率化により、空いたリソースで人を減らすのではなく、法務コンプライアンス部としての価値を発揮できる領域を増やしていければと思っています。
團:
説得が大変だった理由の1つとして、法務コンプライアンス部が普段どのような仕事をしているのか、外からはわかりにくいというのもあります。だから私たちが抱える課題感ももちろん理解されにくい。それであれば、私たちの業務プロセスや課題感を丁寧に共有すれば理解してもらえるんじゃないかと考え、資料を作成して何度も何度も説明して、理解を得て予算が承認されました。
徹底的にツールを検証し、課題解決できると確信してMNTSQを導入
MNTSQ 藤井:
法務コンプライアンス部の課題解決手段の1つとしてDXを推進し、その一環でMNTSQの導入を決断いただいたと思います。他のツールもたくさん見られたと思うのですが、検討から導入までの経緯をお話しいただけますか。
白水:
2024年の4月ぐらいにこの体制でプロジェクトを開始しました。CLMや契約レビューサービス全10社ほどを比較して、3か月程度で、先ほどからお話している課題解決に資すると考えられる2社のサービスに絞りました。
最後に残った2社でトライアルを実施し、システム部門が定めるセキュリティ基準に合致するかどうか、課題解決に必要と考え私たちで洗い出した要件を満たしているのか、実際の業務で使用できそうかを丁寧に確認し、要件ごとに点数をつけ比較しました。MNTSQの営業担当者には、かなり無茶なリクエストを聞いていただいたり、初歩的な質問にも丁寧に答えていただいて感謝しています。機能面について細やかに検討し、また、実際に業務で使用することを想定しながらトライアルをしたおかげで、自分たちの業務フローに落とし込めることを納得しながら選定することができました。

深瀧:
本当に、良くも悪くも予算はないし、トップダウンの指示があるわけでもない。あくまでみんなが持ってる課題を解決したいという思いが推進の源泉にあるので、合うものであれば導入するし、もし合うものがなければ何も導入しない。そのようなスタンスでフラットに選定していました。でもそのスタンスがあるから、課題解決に最適と考えたMNTSQについて、部内および関連部署へも自信を持ってプレゼンして説得できたんだと思います。
MNTSQ 藤井:
よく、手段が目的化してしまってツールを導入した後に全く稼働しないというパターンも少なくはないと思うのですが、皆さんの場合は目的が全くブレずに導入され、しっかり運用にものせられていて素晴らしいと思います。
團:
事業部への利用促進もスムーズに進められたと思います。深瀧さんと白水さんがMNTSQをしっかり理解した上で、機能説明や利用するメリットを自信を持って伝えてくれたのが大きいです。2人とも、普段の仕事ぶりが素晴らしく、事業部からの信頼を得ていたのも、直接的ではないですが、協力を得やすかった重要な要因だと思いますね。
DX推進を迷走させないためには、確固とした理想像を共有すること
MNTSQ 藤井:
最後に、DX推進に関する悩みを持たれている方たちに向けて、実際成功されている皆さまからメッセージをいただけますか。

深瀧:
目の前にある課題は何かを整理し、自分たちが目指す理想の姿と、それを実現するための打ち手を明確にすること。ここがスタート地点であり何より重要だと思います。打ち手の1つであるはずのDXが目的化してしまうと、ゴールを見失って迷走してしまうこともあると思うのですが、逆にそれらが見えていれば、検討の段階でも、導入後の運用までイメージができブレずにプロジェクトを進められますからね。
團:
予算やリソース確保など社内外で様々な調整が必要なタイミングがたくさんあると思います。その時、自分自身がこの課題を解決してこうなりたいんだという姿をしっかりと見定めて、DXチーム全員で共通認識を持てていることが重要だと思いますね。その状態であれば、ツール選定の際にも合理的な判断ができるし、他部門への説得も進めやすいと思います。
白水:
時代の流れ的に、多くの企業にとってDXはもう避けられないと思っています。MNTSQに限っても、国内の多くの大手企業が導入していますし、業界スタンダードになっていくのではないかなと。ナレッジマネジメントに関しては、過去の履歴を蓄積していくものなのでできるだけ早く始めた方がいいですね。
契約交渉の場面を想像しても、ナレッジマネジメントをしている企業としていない企業の差は、将来的に確実に出てきてしまうかなと思います。
兼松法務コンプライアンス部の皆さま、ありがとうございました!