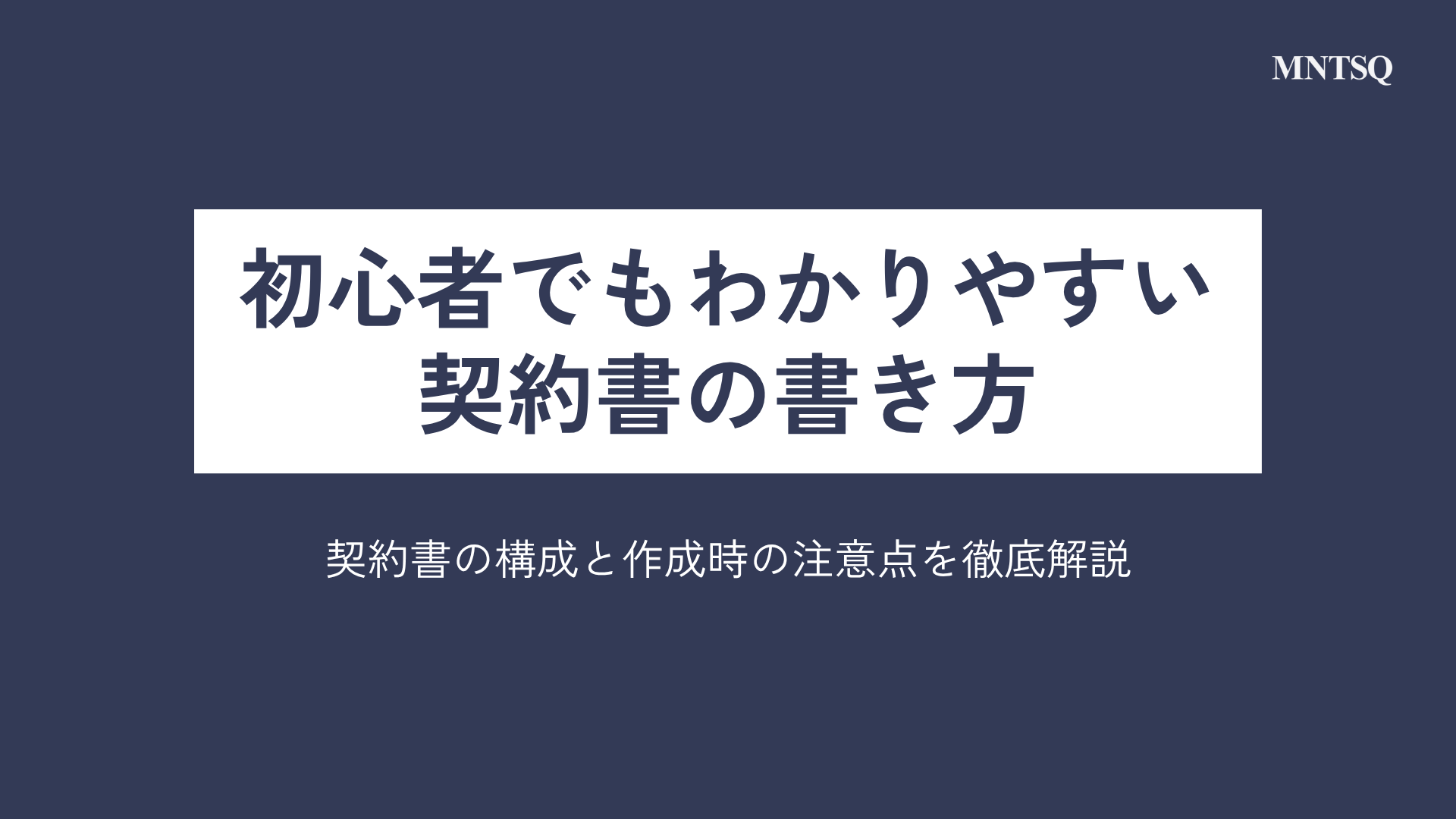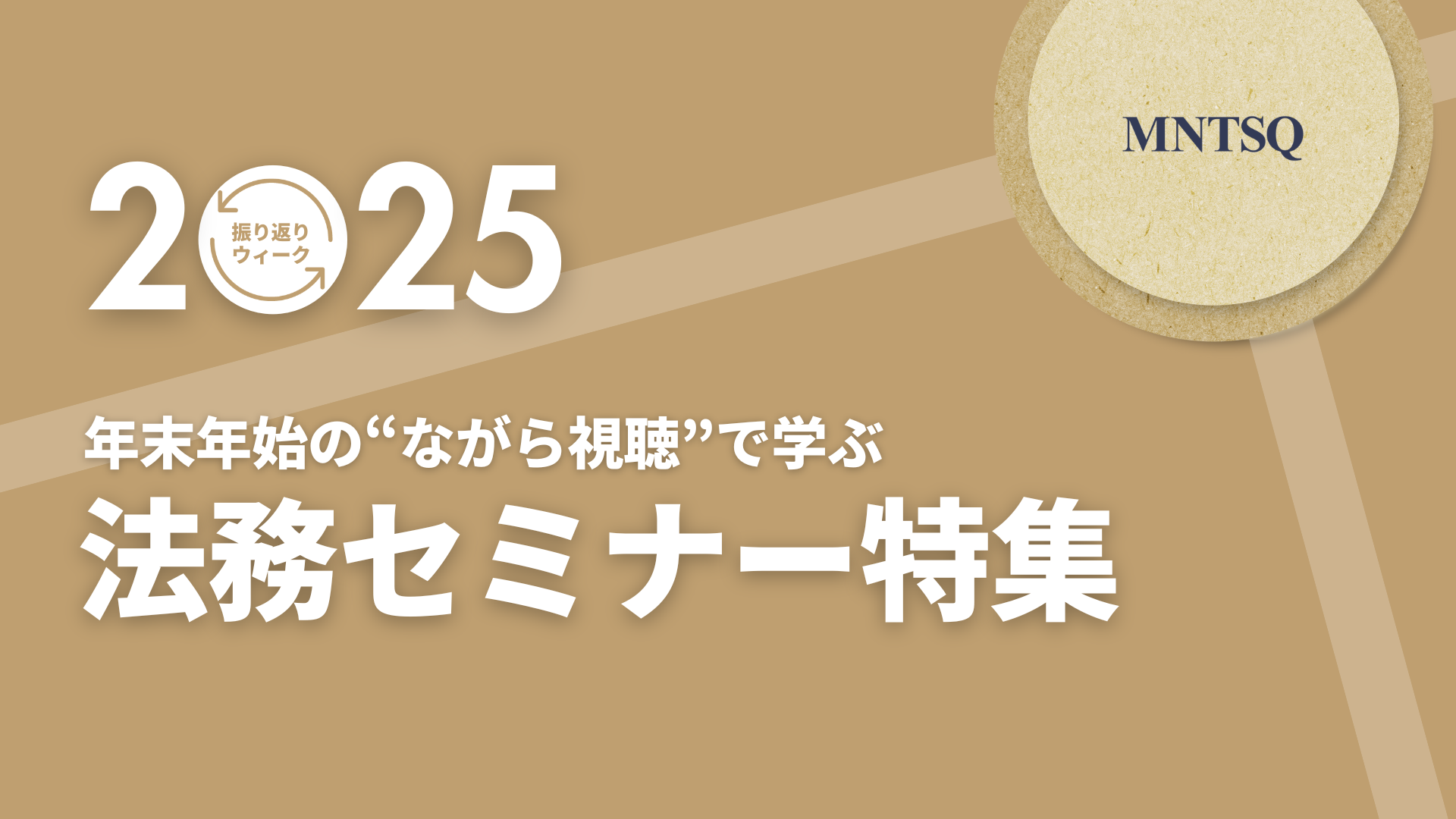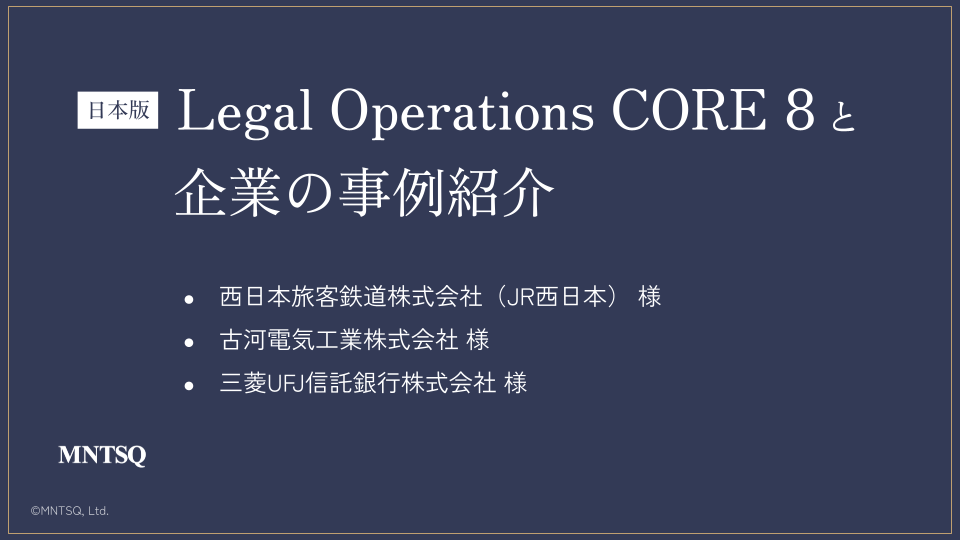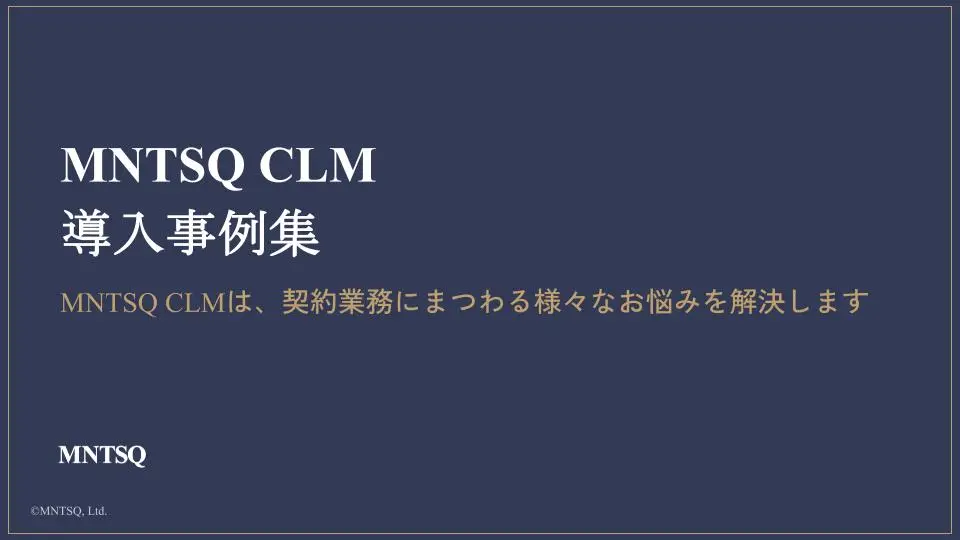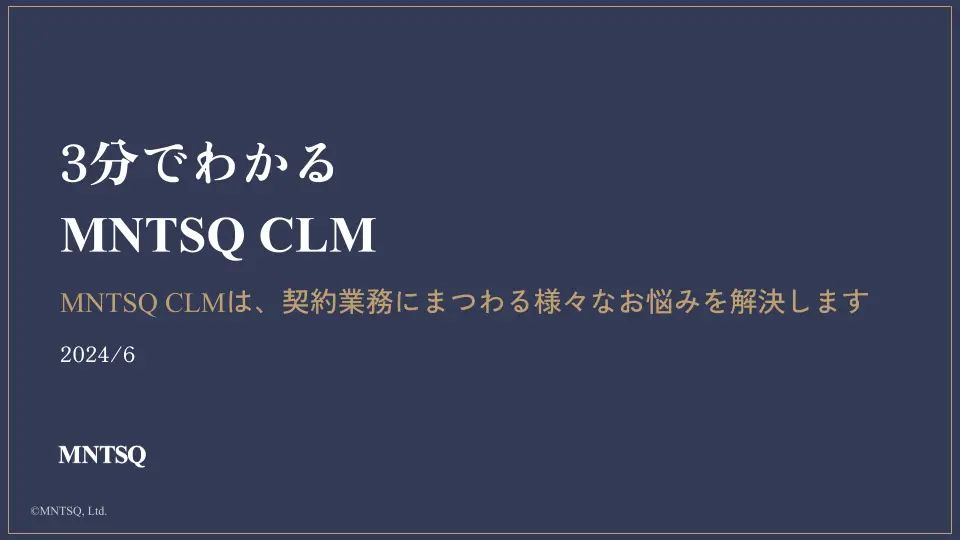契約書とは?
契約書は、契約を結ぶ当事者同士が取り決めた契約内容を文書として明記し、署名や押印などを行って合意を証明する書類です。契約内容の確認だけでなく、紛争時の証拠としても活用できるため、ビジネスや個人取引において極めて重要な役割を持ちます。
契約書が必要な理由
契約書には、契約内容を明確にし、トラブルや法的紛争を防ぐ目的があります。
契約内容と契約合意を明確化するため
契約書は、当事者が合意した内容を具体的に文章で記載するため、契約内容や契約の合意を明確化できます。特に複雑な内容や長期的な契約においては、当事者同士の認識のズレを防ぐ役割も果たします。
取引相手とのトラブルを回避するため
契約書は契約条件や責任範囲を客観的に示す証拠となるため、取引中の誤解やトラブルを防ぐことにつながります。契約途中で何らかの問題が生じた際は、契約書の記載内容に基づいて対応することで被害の拡大を防げます。
法的紛争となった際の証拠となるため
当事者同士の間で契約違反や損害が発生して裁判となった場合、契約書は重要な証拠として機能します。契約書は裁判において契約の存在と内容を立証する手段となるため、書面化しておくことで法的リスクを最小限に抑えられます。
個人契約書と法人契約書の違い
個人契約書はその名の通り個人間の契約、法人契約書は法人間の契約を指します。個人契約書では契約者名や印鑑が実名・実印となるのに対し、法人契約書では法人名・代表者名・会社印が必要です。また、契約主体が法人である場合、印紙税や契約書の保管義務なども発生します。
覚書・誓約書との違い
覚書は契約内容の一部を補足・変更・確認するための文書であり、おもに契約の付属文書として用いられます。一方、誓約書は特定の約束事やルールを遵守することを示す文書で、契約者の義務を明確化する際に使用されます。どちらも契約書とは別で締結するのが一般的です。
契約方法の種類
契約は書面で結ぶ契約書のほかにも、さまざまな方法で成立します。
口頭契約
口頭契約は、書面を交わさずに言葉だけで契約を成立させる方法です。民法上では有効とされますが、後から契約内容を証明することが困難なため、重要な契約ではリスクが高くなります。
契約書
契約書は、契約内容を明文化した上で当事者が署名・押印をして合意の証拠とする書類です。書面化することによって内容が明確となり、契約後のトラブルを未然に防げます。個人間・法人間で契約を結ぶ際の基本となる形式です。
電子契約
電子契約は、クラウドサービスなどを通じて契約書を電子上で作成・締結する方法です。印紙税が不要で、紙よりも双方のやり取りや保管がしやすいという利点があります。電子署名法を遵守すれば、紙の契約書と同様の法的効力も担保されます。
公正証書
公正証書は、法務大臣が任命した公証人が法的手続きに基づいて作成する文書で、契約書よりもさらに強い証明力と執行力を持つのが特徴です。また、契約書が私文書であるのに対し、公正証書は公文書に該当します。公正証書は契約不履行が生じた際に裁判を経ずに強制執行が可能となるため、金銭貸借でよく用いられます。
一般的な契約書の構成と書き方
契約書は、決まった形式と構成に従って作成されます。以下では、各項目の構成や書き方を紹介します。
タイトル
契約書のタイトルは、書類の目的や性質を明確に示す意味合いを持ちます。「業務委託契約書」「売買契約書」など、誰が見ても内容が一目で分かる名称にすることが重要です。
前文
前文には、契約当事者の氏名・住所・法人名・代表者などの基本情報や、契約締結の趣旨を記載します。契約の前提条件や背景を簡潔に記述することで、以降の本文の理解を補完する役割も持ちます。
本文
本文には、契約の具体的内容や各条項が条文形式で記載されます。業務の範囲・支払い条件・契約期間・秘密保持など、当事者間の権利と義務を明記します。曖昧な記述は避け、具体的かつ明確な表現が求められます。
後文
後文では、契約書が正当な手続きで締結されたことや、原本の通数や保管者について明示します。末尾には契約者の名前と住所も記載されます。
契約締結日
契約締結日は、当該契約が法的に効力を持つ起点となる日付です。多くの場合、後文の直後に記載されます。契約期間や契約更新日、契約履行の開始日にも関わるため、正確に記載することが重要です。
署名・記名
契約書には、契約を結ぶ当事者それぞれの署名または記名が必要です。個人契約では署名、法人契約では記名(法人名・代表者名)とするのが一般的です。本人確認やトラブル回避のために、直筆するのが望ましいとされています。
押印・捺印
署名・記名に加えて押印・捺印を行うことで、契約の信頼性が高まります。個人契約では実印や認印、法人契約は会社の実印を用います。印影が不鮮明にならないよう、しっかりと捺印することが重要です。
印紙
契約金額や課税などの一定の条件を満たす契約書を作成する際には、印紙税法に基づいて印紙の貼付が義務付けられています。印紙税額は金額や契約内容によって異なるため、事前に正確な金額を確認しましょう。なお、電子契約では原則として印紙税が不要となります。
契約書を作成する際の注意点
契約書の作成では、曖昧な表現や内容の不備に注意し、法的リスクを未然に防ぐことが重要です。
雛形をそのまま使わない
今日ではインターネット上に契約書のテンプレートや雛形が数多く掲載されていますが、それをそのまま使用するのではなく、必ず契約内容に合わせて修正を加えましょう。雛形をそのまま使用すると、最新の法令や契約内容に合わない条項が含まれたり、雛形としての品質に問題があったりと、トラブルの原因となるおそれがあります。
法律用語に基づいて記載する
契約書上では、俗語や社内用語は避け、できるだけ法律用語を使用しましょう。「契約解除」「損害賠償」といった専門用語を用いることで、記載内容の解釈がぶれにくくなります。
第三者にもわかる内容にする
契約書は当事者間だけでなく、裁判所などの第三者も確認する可能性があります。難解な表現や業界用語を含めて暗黙の了解による省略は避け、誰が見ても理解できるように記載することが大切です。
曖昧な表現は避けて明確に記載する
契約書上では「できるだけ早く」「適宜」などの曖昧な表現を避け、具体的な期限や行為を明示することが重要です。契約条件を明確化することで、解釈の違いによるトラブルを防ぎ、紛争発生時にも根拠として機能します。
具体的な数値を設定する
金額・数量・期間などの数値で表すことができる内容は、可能な限り明確に記載しましょう。具体的な数値設定は当事者間の認識の統一に貢献し、契約内容の誤解や契約中のトラブルを防ぐことにつながります。
長い単語を省略しない
長い単語や一般的には省略して用いられている単語であっても、契約書上では正式名称を記載しましょう。略語や省略形を避けることで、意味の取り違えを防止できます。
締結前にリーガルチェックを行う
作成した契約書は、必ず締結前に専門家によるリーガルチェックを受けましょう。法的な不備や自社にとって不利な項目があれば修正を行い、リスクを最小限にした状態で契約を締結することで、契約後のトラブルを最小限に抑制できます。
複製されないように割印を行う
契約書を締結する際は、信頼性の高い契約文書として機能するよう、不正な複製や改ざんを防ぐための対策も必須です。一般的な方法として、契約書に対して数か所の割印を捺印し、原本を証明する行為があります。
権利と義務を明確にする
契約書では、当事者それぞれの権利と義務を明確に定義することが必要不可欠です。誰が何をするのかを具体的に示すことで、契約履行責任の所在が明確になり、紛争発生時にも有効な証拠となります。
法律に抵触する契約書は有効?
契約は原則として当事者同士の合意に基づいて自由に締結できますが、全てが無条件に有効であるとは限りません。法律に反する内容が含まれている場合、その契約が無効となる可能性があります。
契約書を作成する際は、民法上の強行規定や任意規定、商法上の取締規定などとの整合性を確認することが重要です。
強行規定
強行規定とは、当事者間の契約合意があっても、これに反する契約内容は無効とされる法的ルールです。たとえば、労働者の最低賃金や消費者保護に関する条項などが該当します。強行規定の内容は、当事者同士が合意したとしても、法律によって上書きされます。
任意規定
任意規定は、当事者間で特段の取り決めがない場合に適用される、補完的な法律ルールです。たとえば、売買契約における引渡しの時期などがこれにあたります。
該当項目について契約書で明記されていない場合には民法の任意規定が適用されますが、契約書上で内容を定めていればその取り決めが優先されます。
取締規定
取締規定とは、おもに会社法や商法に基づいて設けられた規定で、企業間の契約における取引の適正性を確保するためのルールです。
たとえば、会社が行う定款の変更手続きや株主総会の決議要件などがこれに該当します。取締規定に違反する契約内容は、無効や取消しの対象となることがあるため注意が必要です。
まとめ
契約書は、双方の合意内容を明文化し、法的トラブルを未然に防ぐための重要な文書です。正確な構成と書き方で、規定に沿った正しい契約書を作成しましょう。
MNTSQでは、法務領域の一連の業務プロセスを変革するサービスを提供しています。大手法律事務所監修の契約書雛型が利用できたり、過去の契約内容に基づいた提案や確認が必要な条項の指摘があったりと、契約書作成に役立ちます。社内にある法務関連データを連携し、契約の作成・審査・管理からナレッジ化までを一気通貫でサポートすることで、リーガルリスクのマネジメントと法務業務の高速化を同時に実現します。興味のある企業担当者は、ぜひ以下からお問い合わせください。