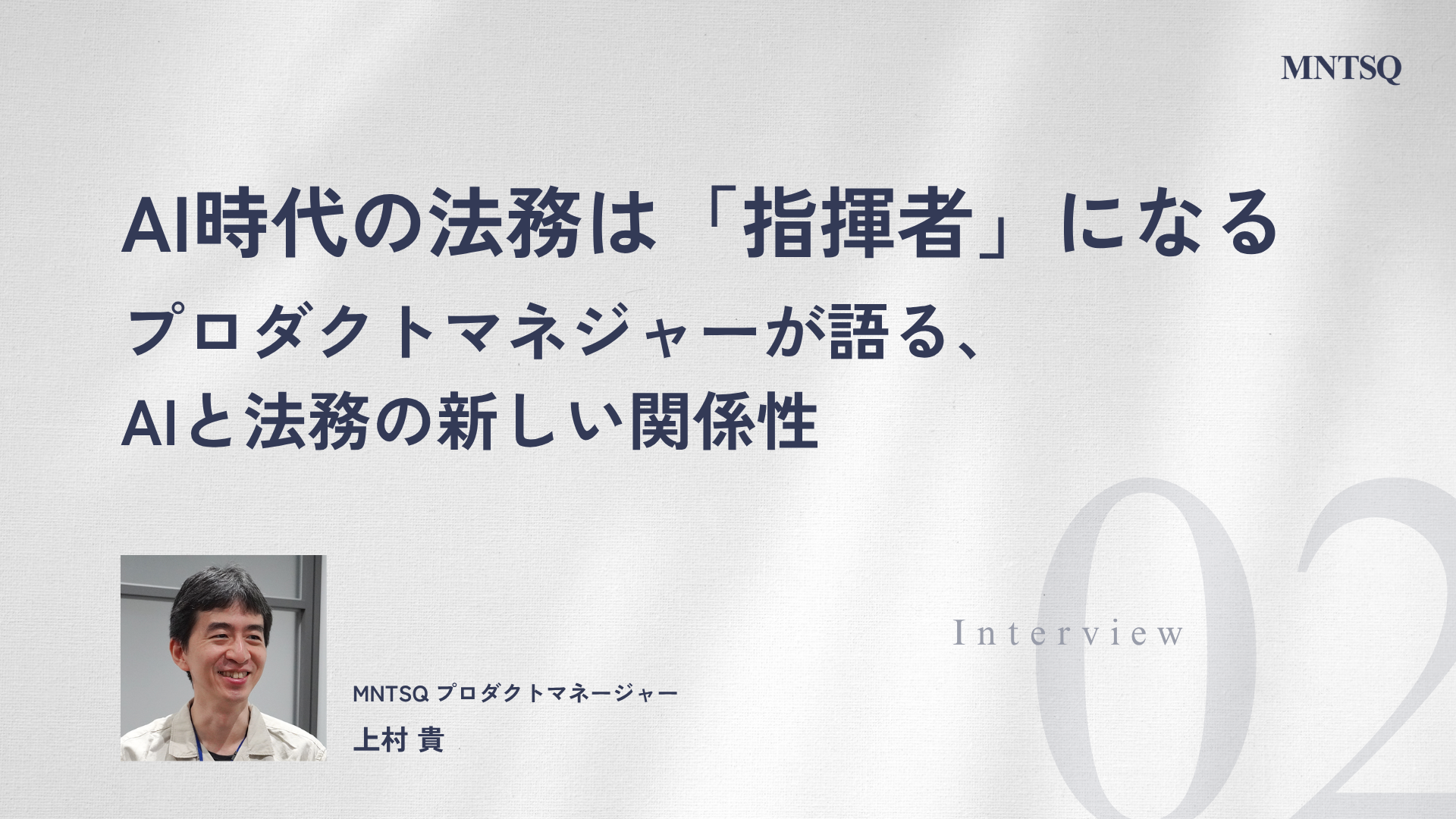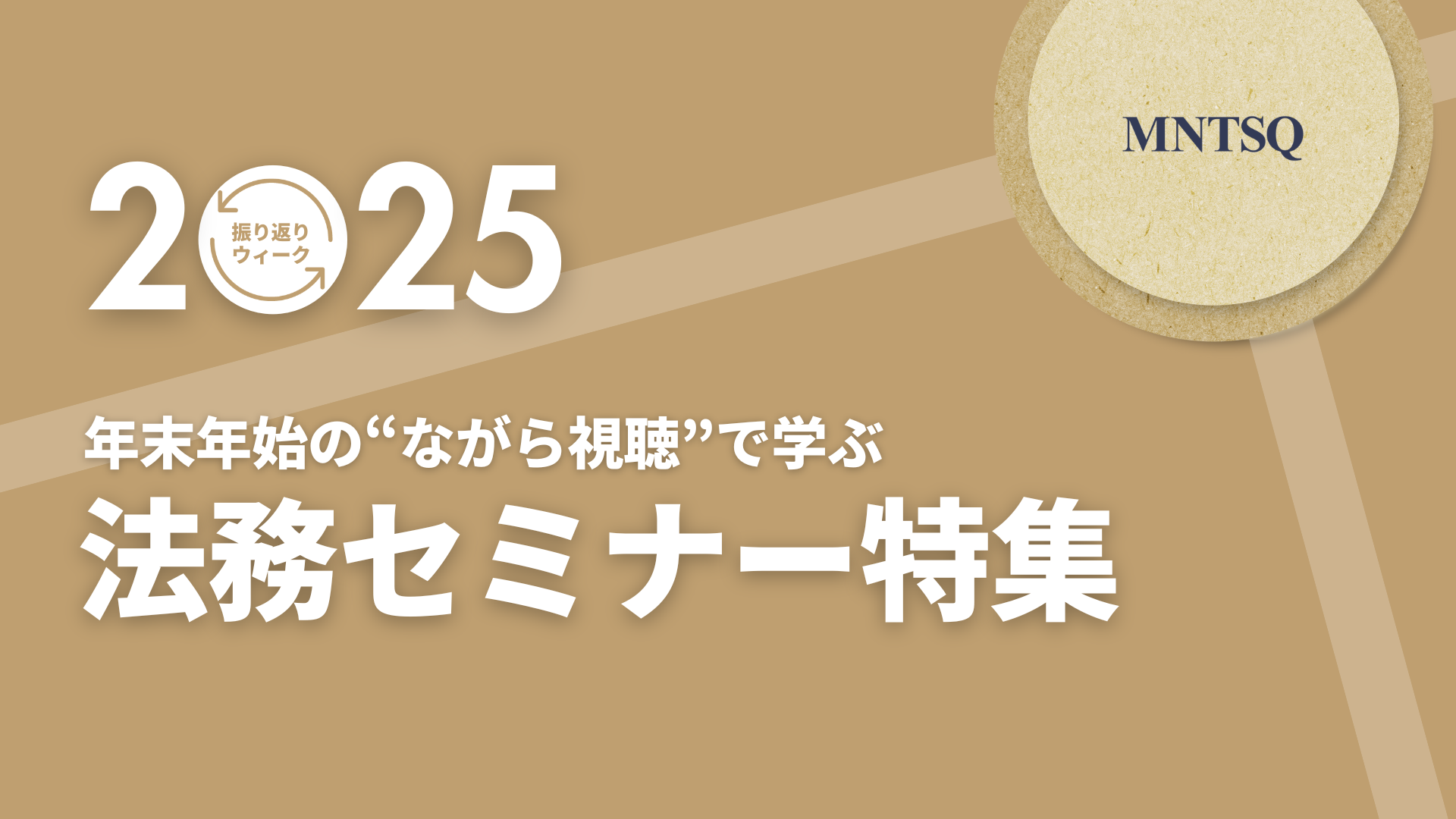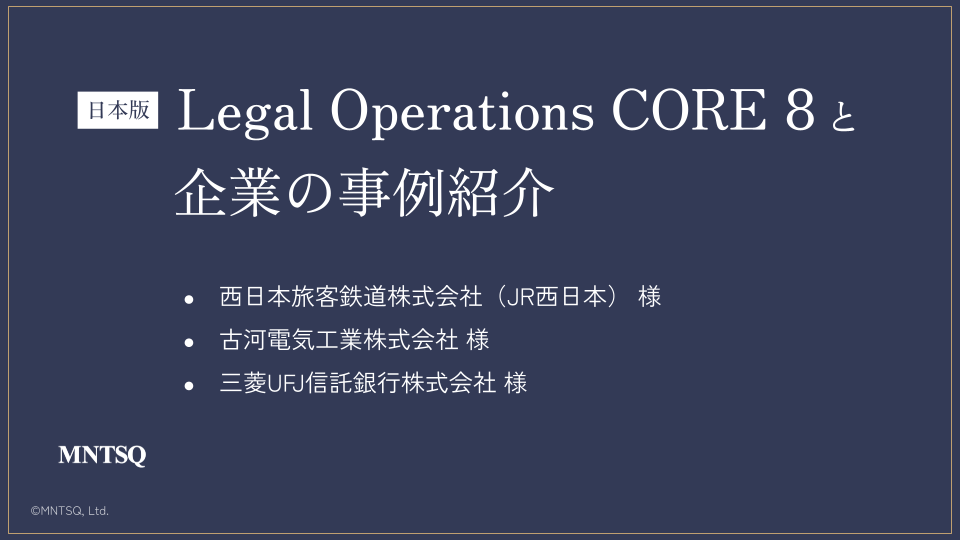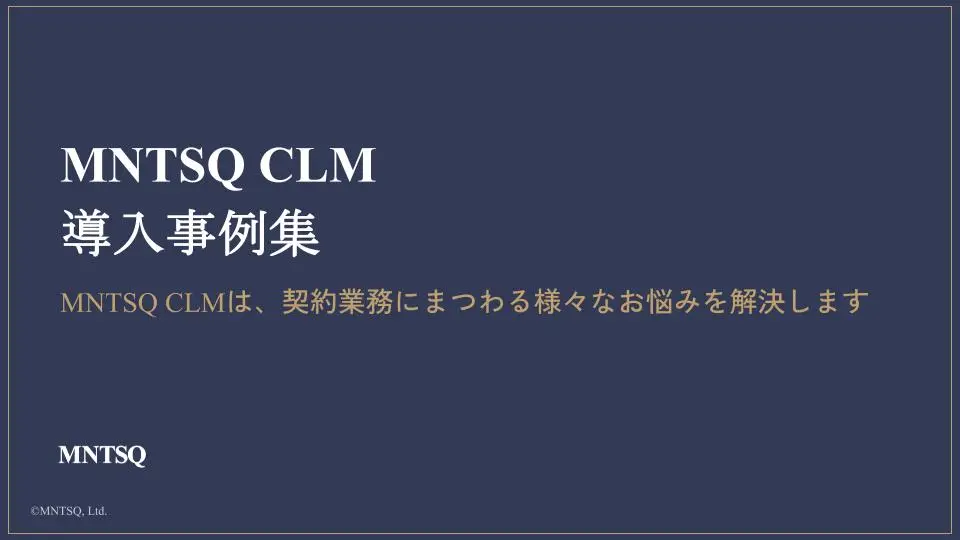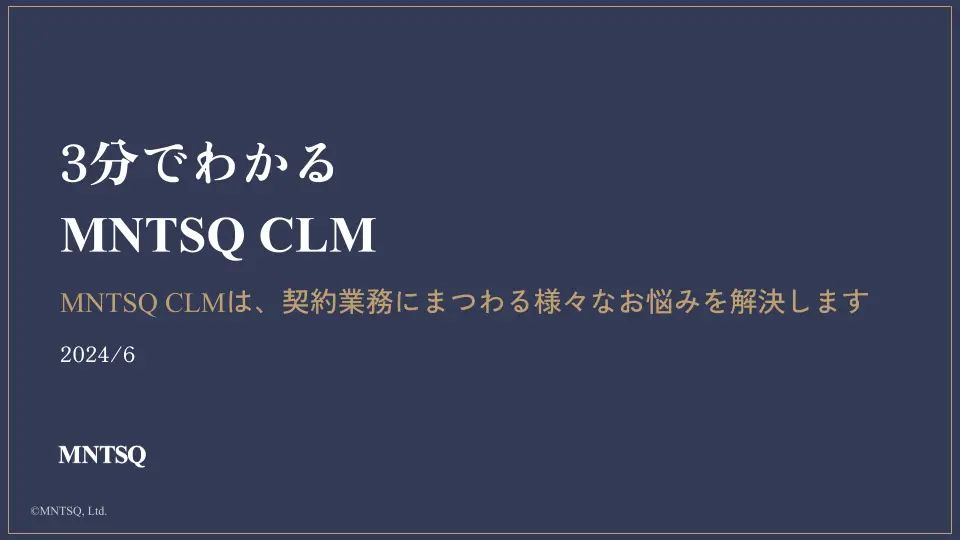契約業務への個人的な「モヤモヤ」を、社会を変える原動力に

——まず、現在のお仕事について教えていただけますか。
上村:
私はMNTSQでプロダクトマネージャー(PdM)として働いています。まだ世の中に馴染みのない職種かもしれませんが、一言でいえば「製品企画・商品企画」の人だと思ってください。
基本的には、お客様にとって最も価値のある製品は何かを考え抜き、それをエンジニアやデザイナーとともにプロダクトへと落とし込んでいく。そんな仕事をしています。
——上村さんはどんな思いから、MNTSQでのプロダクト開発に取り組んでいるのでしょうか。
上村:
私はこれまで大企業からスタートアップまで様々な組織を経験してきましたが、いつも「契約をもっと快適なものにしたい」と考えていました。本来であれば、フェアな契約をスピーディに結び、ビジネスそのものに時間とエネルギーを集中させたい。事業会社で働く人なら、きっと誰もがそう思うはずです。
しかし現実は、あまりにストレスフルでした。特に私自身、転職や異動の直後は、社内の複雑な手続きが分からず途方に暮れることが多々ありました。会社や事業部によってルールも異なり、何をどう進めればいいか分からず、調べるだけで膨大な時間が溶けていく。
やっとの思いで法務部にレビューを依頼しても、数日から数週間待たされることもありましたし、そもそも自分の依頼が正しく伝わっているのか不安になることもありました。正直、契約業務に良い印象はあまりなかったですね(笑)。
ただ、かといって自分一人で判断できるほどの法務知識もない。だから「ボタンをクリックしていくだけで契約が完了するようなシステムがあればいいのに」と、ずっと思っていました。この個人的な課題意識を、社会を変える原動力につなげたい。その思いが、MNTSQでのプロダクト開発の原点です。
転機は突然に。AIが見せた「魔法」
——昨今AIの進化も加速していますが、MNTSQとしてはAIをどのように開発に反映させているのですか。
上村:
私にとって、生成AIは「今までできなかったことを可能にする魔法」のような存在です。
私が入社した当初、MNTSQでは機械学習をベースにした独自モデルが主力でした。それも十分に強力でしたが、何かを処理させるには膨大な学習データと時間が必要だったんです。
そんな中、登場したのが生成AIでした。「ChatGPT」が世の中で騒がれ始めた頃、法務経験のある同僚と「生成AIで何ができるか」を日々模索していましたね。
転機が訪れたのは、「Claude 3.5 」の登場です。それまで難しいだろうと思っていた契約書のチェックを試してみたところ、驚くほど的確なアウトプットが返ってきたんです。
「これは、まさに技術革新だ」と、衝撃を受けました。 すぐに新規プロダクトの企画に取り掛かり、それが現在の「AI契約アシスタント」の原型となっています。
一方で、この“魔法”をどう業務に組み込むのが正解なのかは、正直まだ誰にも分からない。今も試行錯誤しながら、新しい活用法を探っている最中です。
AIは「アシスト」か、「自動化」か。MNTSQが掲げる“二刀流”という思想
——いまAIはどんどん進化していく一方で、同時に生まれる課題もあると思います。そうした現状を上村さんはどのように捉えていますか。
上村:
おっしゃる通り、AIはあまりに汎用的なので、使い方を間違えると意図しない結果を招く危険性もあります。たとえば日常生活でよく触れるSNSでも、AIを悪用したりすれば、とんでもないことになる可能性もあると思ってます。
そこで重要なのが、「AIをどう使うか」という視点です。これには大きく分けて2つの方向性があると考えています。一つは「人間の仕事をAIがアシストする」という考え方。そしてもう一つが「人間の代わりにAIが仕事をする=自動化」です。
MNTSQでは、この「アシスト」と「自動化」を最適なバランスで組み合わせる “二刀流” を目指しています。
——「二刀流」とは、具体的にどのような状態を目指すのでしょうか。
上村:
AIで自動化できる領域を広げつつ、人間にしかできない判断が求められる領域では、AIによるアシストを手厚くしていく、という考え方です。
たとえば契約業務の全体量を100とすれば、将来的には70〜80はAIが自動で担えるようになるかもしれません。しかし、残りの20〜30は、AIだけでは判断できない領域として残ると考えています。
なぜなら、AIは基本的に必要な情報のインプットと正しい指示がないと、期待通りに動かないからです。ビジネスの複雑な背景や取引相手との信頼関係といった、言語化しきれない“文脈”を汲み取った最終判断が必要な領域は、人間の仕事として残り続けるはずです。
——代表の板谷も「法務の仕事をゼロにするのではなく、人間が本当に考えるべきことにフォーカスできる世界を作りたい」と話していますよね。
上村:
そうですね。なので法務の仕事を全部AIに任せる、という発想はしていません。
AIに的確な指示を出すのは非常に難しいんです。たとえば、単に「この契約書をチェックして」とAIにお願いするだけだと、AIの“気分次第”のアウトプットが出てきてしまい、業務には使えません。
だからAIに「この観点でチェックして」と、おさえてほしいポイントを情報として与えることが重要です。AIは驚くほど素直なので、これだけでアウトプットの精度は格段に上がります。
AIを“育てる”。正解なき試行錯誤の道のり
——その「観点」という、人間であれば思想のようなものをAIにどうインプットしていくかが重要なんですね。
上村:
ええ。さらに一段階進んで、「この取引先とは過去にこういうビジネスをしていて、今回の商談ではこういうふうな取り組みをしたから、この契約書を作ったんです」といった、より深い文脈をインプットすれば、「この条文は事前の合意と違うのでは?」といった高度な指摘も可能になります。
ただ、こうした文脈をすべてインプットするのは現実的ではありません。だからこそ、最終的には人間の総合的な判断が入る余地が必ず生まれるんです。
——AIをプロダクトに落とし込む上で、開発プロセスはどのように進めているのですか?
上村:
まずPdMの立場からすると、常にお客様が解決したい課題から逆算して考えます。「その課題を解決できるAIのアウトプットは何か?」と。そして、そのアウトプットを出すために「AIにはどんな情報(インプット)が必要か?」を考えます。
そして、「その必要な情報がどこにあるのか」というのが次の課題です。システムの中にある情報もあれば、人の頭の中にしかない「知見」のようなものもある。
そういった様々な情報をどう組み合わせ、人の知見をどうやって「形式知化」してシステムに組み込むか。チームみんなで、最適なモデルを考えています。
——そのプロセスにおける、具体的な試行錯誤についても教えていただけますか。
上村:
日々、みんなで実験を繰り返しています。少し振り返ってみると、一見簡単そうな指示を出す「ステップ1」の機能ですら、最初の頃はうまくいかなかったんです。
「1から10の観点でチェックして」と指示しているのに、観点6が抜けたり、なぜか観点11が出てきたりとか。いわゆる「ハルシネーション(AIがもっともらしい嘘をつく現象)」が起きて、使い物になりませんでした。
そこからAIの進化によって、求める回答が一気に得られるようになりました。これは様々な生成AIを試す中で、発見したことです。今の技術ではできないことも、1年後には当たり前にできるようになっている。そんなことが普通に起こると思っています。
元々、私が昔夢見ていたのは、社内のポータルサイトに契約書をアップロードしたら、「ここは注意してね」「次はこれをやってね」とAIが全部案内してくれる世界でした。
その第一歩は、もうすぐ踏み出せそうです。ただ、それはあくまで簡単な契約の話です。より難しい契約では、やはり人間の判断を残し、AIはあくまでアシストに徹する。その切り分けが重要だと考えています。
AI時代の法務担当者は、オーケストラを率いる「指揮者」になる

——今後、法務担当者の役割はどのように変化していくと考えますか。
上村:
法務担当者は、大きく2つの役割を担うことになると考えています。
ひとつは、業務内容に応じて「これはAIに任せる」「これは人が深く審査する」と判断し、AIを使いこなす「指揮者」としての役割。ふたつめは、AIが集めた情報をもとに、事業の将来を左右するような重要な意思決定を行う「専門家」としての役割です。
MNTSQとしてはその判断を助けるために、AIが効果的にアシストできる環境をつくりたいと考えています。
——そうなると、法務担当者の仕事はどんどん楽になるというよりは、逆に難しい判断が求められるようになり、より専門性が高まるイメージでしょうか。
上村:
そう言っても過言ではないと思います。
私たちとしても、法務業務の「単純な効率化」が目的ではありません。法務の方が付加価値の低い単純作業に忙殺されていて、本来もっと時間をかけるべき付加価値の高い仕事に集中できていない。私は、この状態が大きな課題だと考えています。
定型的で反復的な作業はAIに任せ、新規事業の立ち上げやハイリスクな案件のアセスメントといった、本当に頭を使うべき仕事に時間と情熱を注いでほしい。 法務の方も、本当はそういう仕事がしたいはずですから。
「AIに仕事が奪われる」と懸念する声もありますが、実際は単純作業がなくなる一方で、「AIを使いこなす」という新しいスキルが求められるはずです。
それにこれは契約業務に限った話でもありません。マーケティングやセールスなど、あらゆる職種で単純作業はAIに置き換わっていき、人間の仕事はより専門的になっていくはずです。
——AIに仕事が奪われる、という話もよく聞きますが、単純にそうではなさそうですね。
上村:
そうですね。単純作業はなくなっていくので、ある意味厳しい社会になるかもしれません 。ですが、同時に「AIを使いこなす」という新しいスキルが求められ始めています 。
だからこれからの時代は、AIにはできない自分だけの「武器」を作ることが、とても大切になると考えています。また専門性だけでなく、俗に言う「ヒューマンスキル」が大事な世の中になっていくかもしれません。
ポジティブループを生み出す、MNTSQの「3つの強み」
——最後に、MNTSQが提供する「AI契約アシスタント」ならではの価値についてお聞かせください。他社もAI活用に取り組む中で、MNTSQだからこそ提供できる独自性とは何でしょうか。
上村:
AI契約アシスタントの最大の価値は、使えば使うほど業務ナレッジがAIに蓄積され、賢くなっていく「ポジティブなフィードバックループ」を生み出せる点にあります 。そして、その循環を支える他社にはない強みが、大きく3つあります。
まず一つ目が、大企業への圧倒的な導入実績から生まれた、安全で堅牢な「ナレッジのダム」機構です。
すでに1,000社以上の大企業に導入されており、数万人規模の利用に耐える堅牢なシステム基盤には、膨大な業務ナレッジが集約され続けています 。この「ナレッジのダム」機構は、AIを活用して業務を効率化・高度化するための、他に類を見ない資産です。
二つ目は、「日本トップクラスの法律事務所の知見」を活用できる点です。
MNTSQは、長島・大野・常松法律事務所をはじめとする、日本トップクラスの法律事務所の知見をプロダクトに組み込んでいます。これによりお客様はゼロからAIを教育するのではなく、法務のベストプラクティスという「巨人の肩」の上からAI活用をスタートできるのです。
そして三つ目は、最後のワンマイルまで支える「伴走型のコンサルティング」体制です。
どんなに優れたプロダクトも、現場で使われなければ意味がありませんが、MNTSQのコンサルタントは、大企業の法務・契約業務やDXに精通し、AIの特性も深く理解したプロフェッショナル集団です。お客様のDXを成功に導くために、最後のワンマイルまで徹底的に伴走するコンサルタントの存在は大きな強みです。
——たしかに実際に導入いただいたお客様から、MNTSQのコンサルタントの伴走を魅力に挙げる声をよく聞きます。それでは最後に、読者の方へメッセージをお願いできますか。
上村:
MNTSQは単なるプロダクト会社ではありません。お客様がDXを成し遂げ、成功を収められるまで責任を持って伴走する集団です。
私自身が感じてきた契約業務への“モヤモヤ”を、テクノロジーの力で解消したい。そして、誰もがフェアな合意にたどり着ける社会を実現する。
私たちは、その未来を本気で創り出せると信じていますし、そのプロセスに心からワクワクしています。ぜひ、これからのMNTSQに期待してください。