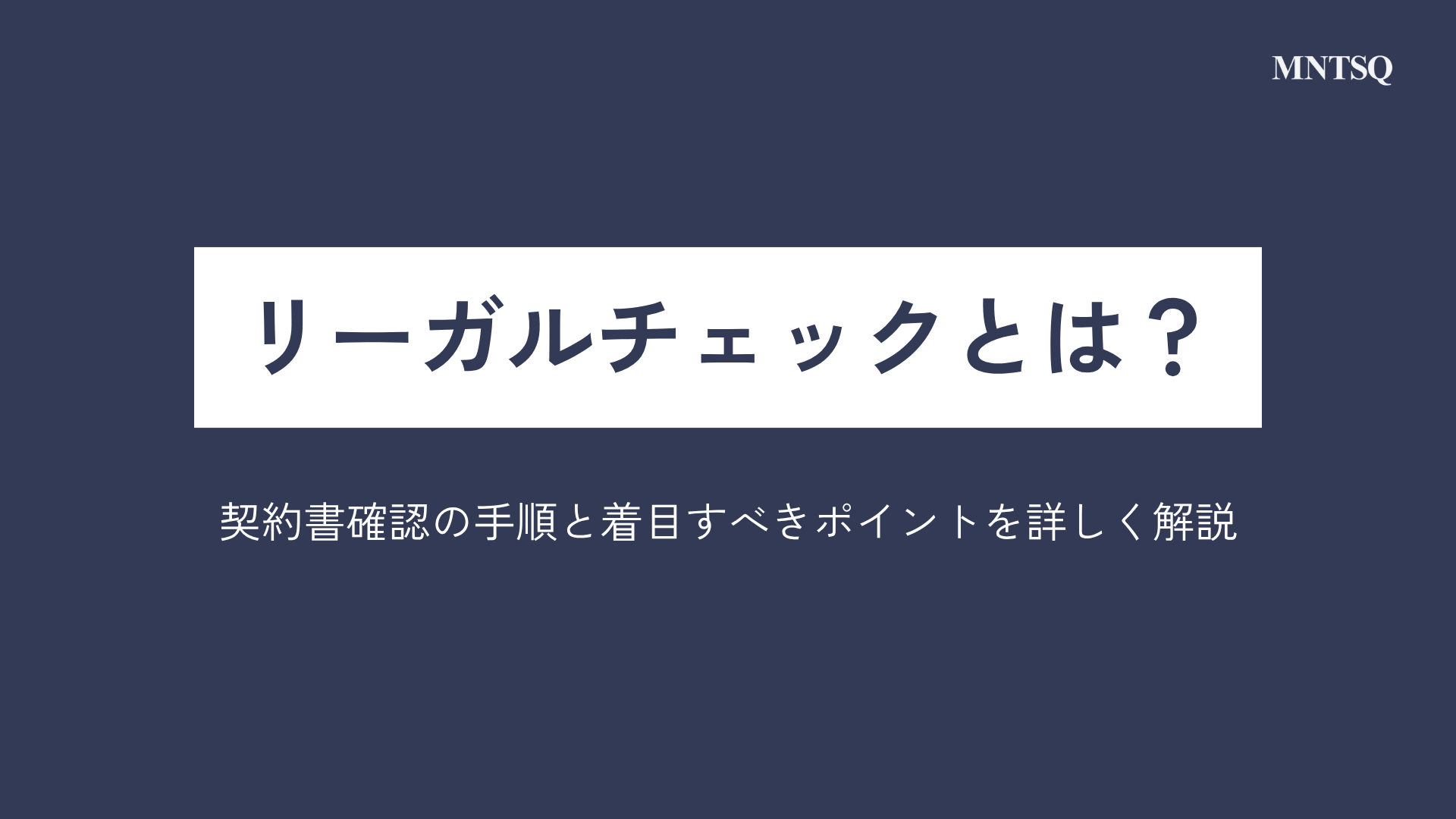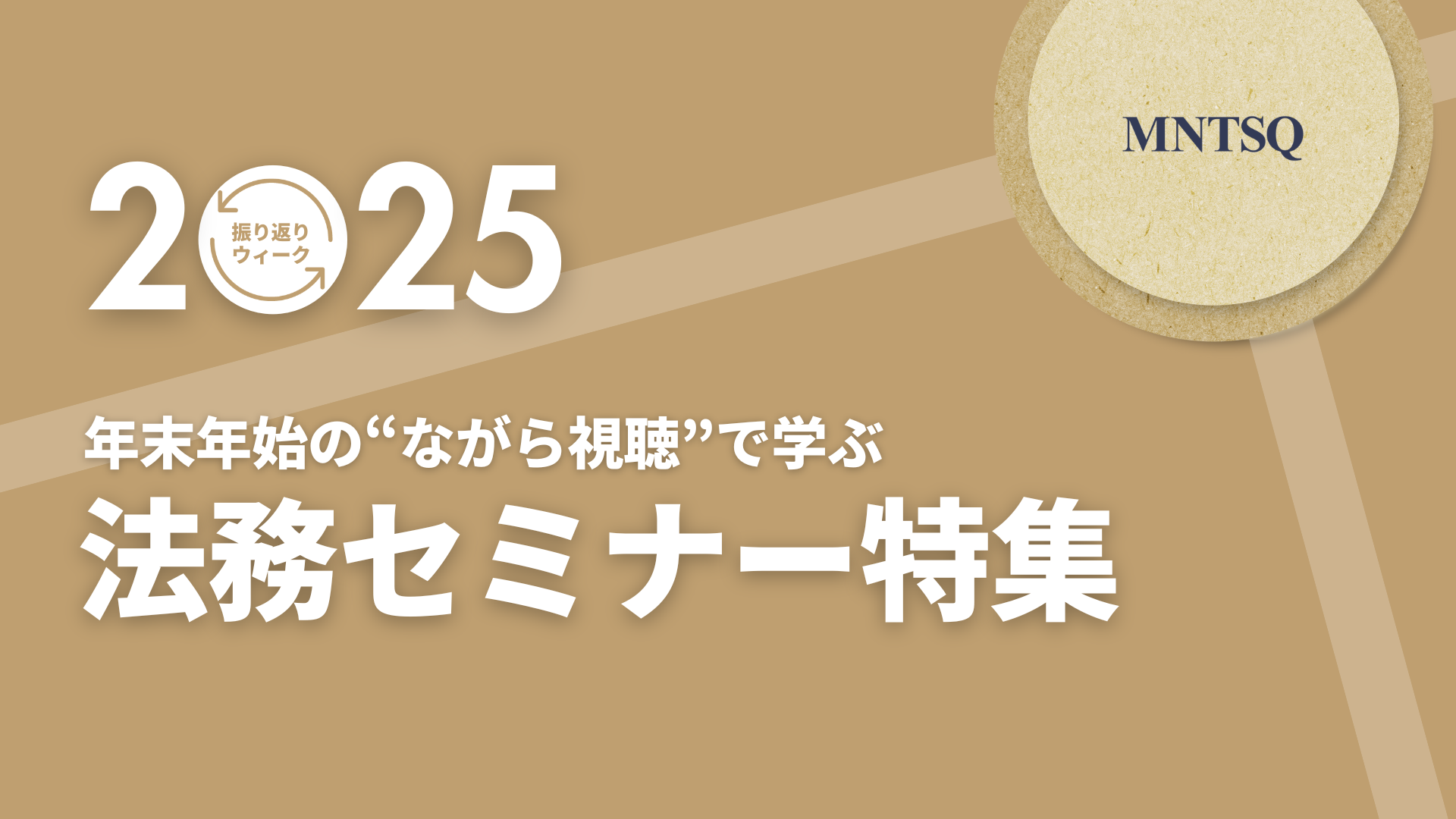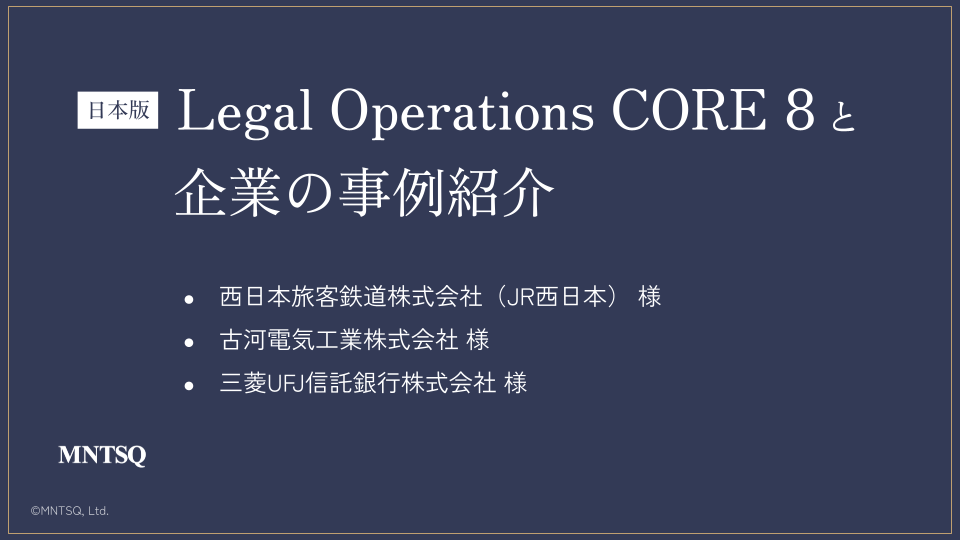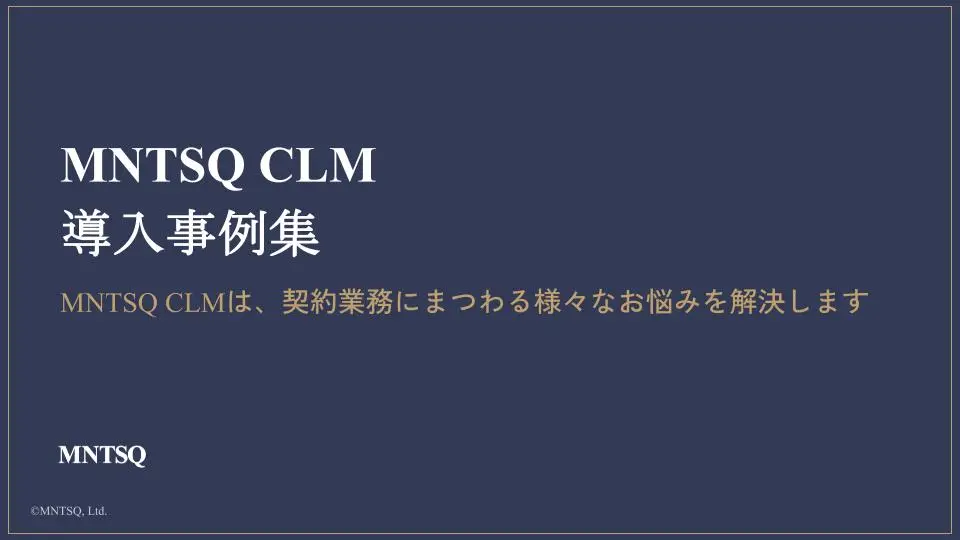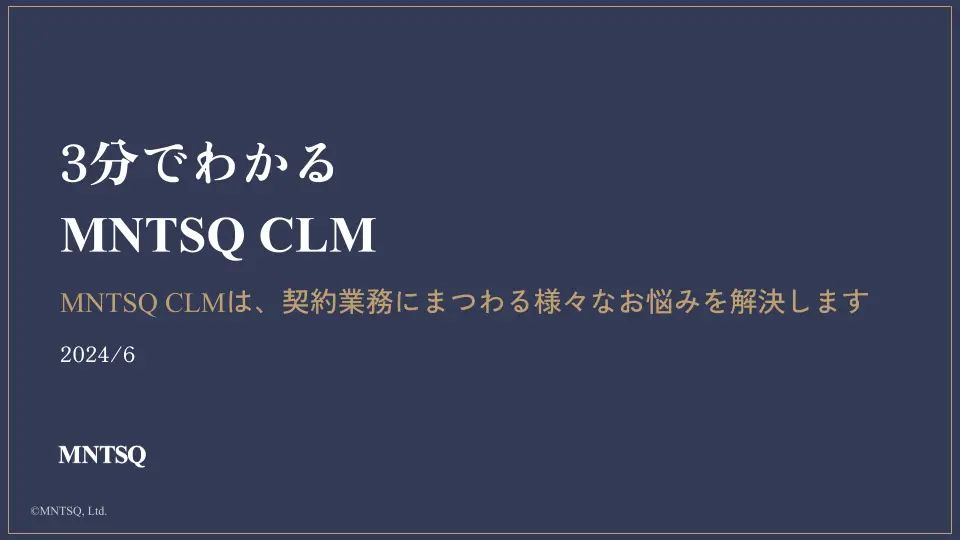契約書のリーガルチェックとは?
契約書のリーガルチェックは、契約内容が法的に適切かどうかを専門的な観点から確認する作業を指します。契約書上の法令違反・曖昧な表現・自社にとって不当な条項などを事前に洗い出し、契約トラブルを未然に防ぐ目的があります。
特に複雑な契約や金額の大きい取引では、法務部門や弁護士による事前のリーガルチェックが必要不可欠です。
リーガルチェックの実施が重要な理由
契約書を作成・締結する際は、法的リスクを回避し、円滑な取引を実現するためのリーガルチェックが欠かせません。
法令違反や法的紛争を事前に回避できる
契約書には、法令に違反するリスクや、将来的に法的トラブルを招く可能性のある表現が含まれることがあります。
リーガルチェックを行うことで、このような不備を早期に発見し、必要に応じて修正可能です。リーガルチェックの実施により、訴訟や損害賠償などの重大な問題を未然に防止できます。
契約が無効になる可能性を回避できる
契約内容に法令に反する条項が含まれていたり、契約書の記載に不備があった場合、その契約が無効と判断されるケースがあります。
リーガルチェックでは、契約を有効とする上での要件や必要事項が満たされているかどうかを確認します。正確なチェックにより、契約が無効となるリスクを回避できます。
トラブルに発展した際の影響を低減できる
契約締結後に万が一契約トラブルが発生した場合でも、契約書にトラブル発生時の明確な条項や対応方法が記されていれば、解決までの時間とコストを大幅に軽減できます。法的根拠に基づいて不測の事態に備えた条文を盛り込むことは、企業のリスクマネジメントにとって重要です。
自社に不利な契約条項を是正できる
相手方の提示する契約書には、自社にとって不利な内容が含まれていることがあります。リーガルチェックではそうした条項を洗い出すことができ、必要に応じて修正・交渉する際の根拠も明示できます。
自社の利益を守りつつ対等な立場で契約を結ぶ上でも、リーガルチェックは重要な役割を果たします。
契約するビジネスの内容を明確化できる
リーガルチェックを通じて、契約書に記載されている業務内容・責任範囲・納期・報酬などが明確かどうかもチェック可能です。不明確な点や解釈に余地が生まれる点を修正することで、双方の認識違いを防ぎ、ビジネスをスムーズに展開できます。
社内でリーガルチェックを行う一般的な方法
自社内で契約書のリーガルチェックを実施する際は、担当部署間での連携や明確な依頼フローの作成が必要です。
1.契約書チェックの申請・受付
契約書のリーガルチェックが発生した場合、はじめに関係部署が法務部門へ申請を行い、契約書案を送付します。申請時には契約の目的や背景、締結予定日なども共有することで、より正確なチェックを受けられます。
2.契約書全体を把握して修正点を挙げる
申請を受理した契約書は、法務部門の担当者が条文全体を通読し、内容の整合性・表現の明確さ・法的妥当性などを細かくチェックします。
特に自社に不利な条項や曖昧な表現がないかは重要なポイントで、必要に応じて修正案を提示するケースもあります。リーガルチェックの担当者は、契約の背景や契約内容を正しく理解していることが求められます。
3.部署担当者へ修正点のフィードバック
法務部門によるチェックを終えたら、修正点や改善点を担当者へフィードバックします。文面の変更点だけでなく、修正の意図や背景も説明し、関係者間の認識を統一しましょう。口頭だけでもかまいませんが、正確な記載のためにも文書を交えてやり取りするのが望ましいです。
4.契約相手との交渉
契約書の修正点を明確化したら、その内容をもとに契約相手との調整・交渉を行います。相手方の理解を得られるよう、法的根拠を示しながら交渉を進めましょう。交渉記録は後日の証拠にもなるため、文書で残しておくと安心です。
5.契約書の締結
交渉の上、最終的に合意が取れた内容で契約書を修正し、署名・押印を行って正式に締結します。締結後の契約書は改ざん防止のために割印を押印し、社内で適切に保管・管理しましょう。リーガルチェックの経過記録もあわせて保存しておくと、後のトラブル対応にも役立ちます。
なお、これまで紹介した「申請・受付」「チェック」「フィードバック」「交渉」「締結」までの一連のやりとりは、MNTSQ CLM上でまとめて実施できます。
案件の申請からステータス管理、修正点のやりとり、契約書の保管までワンプラットフォームで完結するため、メールや共有フォルダを探し回る手間もなく、法務部門と事業部のコミュニケーションがスムーズになります。
弁護士にリーガルチェックを依頼する場合の流れ
専門性が求められる契約内容のチェックでは、弁護士に依頼する方法も有効です。
1.担当部署で契約書と申し送り事項を用意する
リーガルチェック案件が発生したら、担当部署で契約書案に添付する申し送り事項を準備します。申し送り事項には契約の目的・取引先情報・交渉経緯などを記載し、弁護士が契約背景を正確に把握できるように内容を整理しましょう。
情報が不足していると適切なチェックが困難になるため、必要な資料は全てそろえる必要があります。
2.チェックの依頼・契約書の送付
依頼の準備が整ったら、弁護士へ正式にチェックを依頼し、契約書と申し送り事項を送付します。セキュリティを重視し、電子上のやり取りの場合はパスワード付きファイルやクラウドを経由して送付しましょう。あらかじめチェック完了の希望日時も伝えると、スムーズにチェックが進行します。
3.フィードバックの確認
弁護士からのフィードバックを受け取ったら、修正点や指摘された内容を丁寧に確認しましょう。不明点があれば追加質問を行い、弁護士とやり取りしながら解釈のすり合わせを行うことが重要です。
4.契約相手との交渉
フィードバックをもとに契約相手へ修正案を提示し、交渉を行いましょう。弁護士の助言を得ながら対応すれば、自社に不利な条件の修正や両者の適切な妥協点を見つけやすくなります。
契約交渉は法的根拠を示しながら行い、必要に応じて記録を残すことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
5.契約書の締結
最終合意に至った契約内容で書類を修正し、署名・押印を経て正式に契約を締結します。締結後は原本を適切に保管し、社内の対応履歴も整理しておきましょう。
リーガルチェックの際に着目すべきポイント
ここからは、契約書の妥当性を見極めるために、リーガルチェックにおいて確認すべきポイントを解説します。
契約書の内容に問題がないか
リーガルチェックで最も重要なのが、契約書に記載された内容のチェックです。契約書の内容が契約目的に即しているか、不明確な表現や抜け漏れがないかなどをくまなく確認しましょう。
なかでも損害賠償・契約期間・契約解除条項・秘密保持・権利義務の範囲などは、トラブルの元になりやすいため詳細なチェックが必要です。
また、相手方の要望を一方的に飲んでいないか、自社に不利な内容がないかも重要なチェックポイントです。全ての条項が具体的かつ明確な表現で記載されているかを厳しく見極め、法的トラブルを未然に防ぐことが求められます。
契約書の形式に問題がないか
契約書の内容だけでなく、体裁や形式にも問題がないか確認を行います。タイトル・契約開始日・当事者の記名や押印などの基本的な要素が正しく記載されているか、形式に不備がないか必ず目を通しましょう。契約を無効にしないためにも、細かい番号のズレやページの抜け落ちにも注意が必要です。
不明な用語が用いられていないか
契約書では専門用語や法律用語が多く使用されますが、意味が曖昧な表現や解釈に幅がある用語が使用されている場合は注意が必要です。誰が読んでも同じ解釈になるよう、可能な限りわかりやすい表現や明確な定義を用いましょう。
取引目的に沿った内容になっているか
契約書の記載内容が、実際の取引目的と一致しているかを確認することも重要なポイントです。業務範囲・納品物の内容・支払い条件などが現場の認識とずれていると後々のトラブルの原因となるため、実務と照らし合わせて問題がないかを確認しましょう。
トラブル発生時の対応方法が明記されているか
契約上のトラブルは発生しないのが一 1番ですが、万が一のトラブル発生時に備えた対応策を定めておくことも重要です。トラブルの長期化や損害の拡大 肥大化を防止するためにも、契約書内にトラブル発生時の対応方法が明記されているか、紛争解決方法に関する条項があるかを必ず確認しましょう。
関連するほかの契約書と整合性が取れているか
複数の契約書が関連している場合や過去に類似の契約を結んでいる場合は、それぞれの内容に矛盾がないかを確認する必要があります。基本契約書・個別契約書・秘密保持契約書・業務委託契約書などの複数の契約を締結する際は、それぞれの契約書の間で整合性が取れているかを確認しましょう。
リーガルチェック業務を弁護士に依頼する場合の費用
弁護士にリーガルチェックを依頼する場合、費用相場は契約書1通あたり数万円程度が一般的です。ただし、契約書の分量・難易度・緊急度・専門分野によって価格は変動します。
また、継続的にリーガルチェックを依頼する場合は、顧問契約を締結するのがおすすめです。月額顧問料は数万円〜数十万円程度が相場のため、依頼する業務量や費用対効果を考慮して検討しましょう。
まとめ
リーガルチェックは契約書における法的リスクを回避し、トラブルを未然に防ぐために不可欠な業務です。実施の流れやチェックポイントを理解し、リーガルチェック体制を最適化しましょう。
MNTSQでは、法務領域の一連の業務プロセスを変革するサービスを提供しています。社内にある法務関連データを連携し、契約の作成・審査・管理からナレッジ化までを一気通貫でサポートすることで、リーガルリスクのマネジメントと法務業務の高速化を同時に実現します。興味のある企業担当者は、ぜひ以下からお問い合わせください。