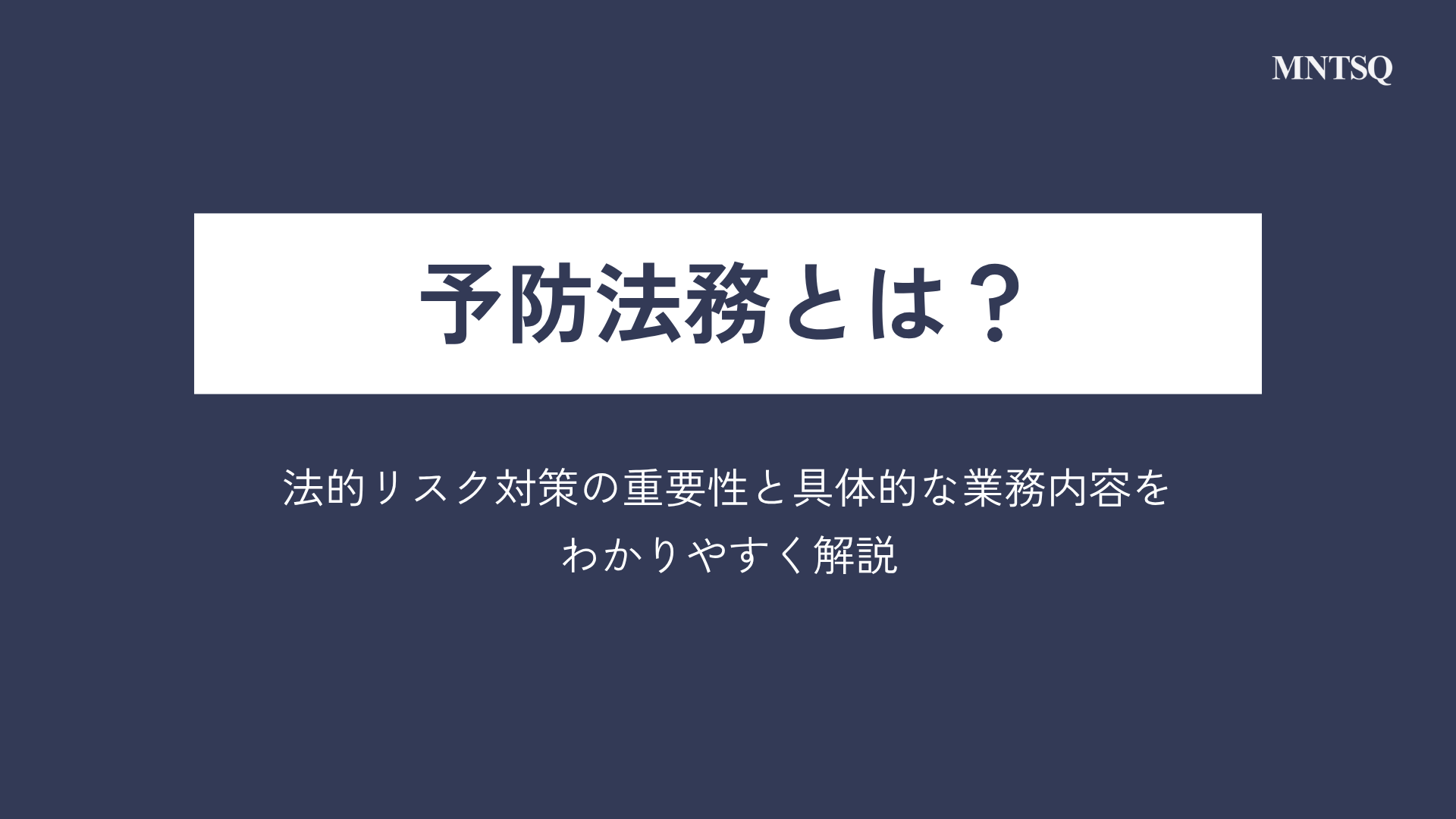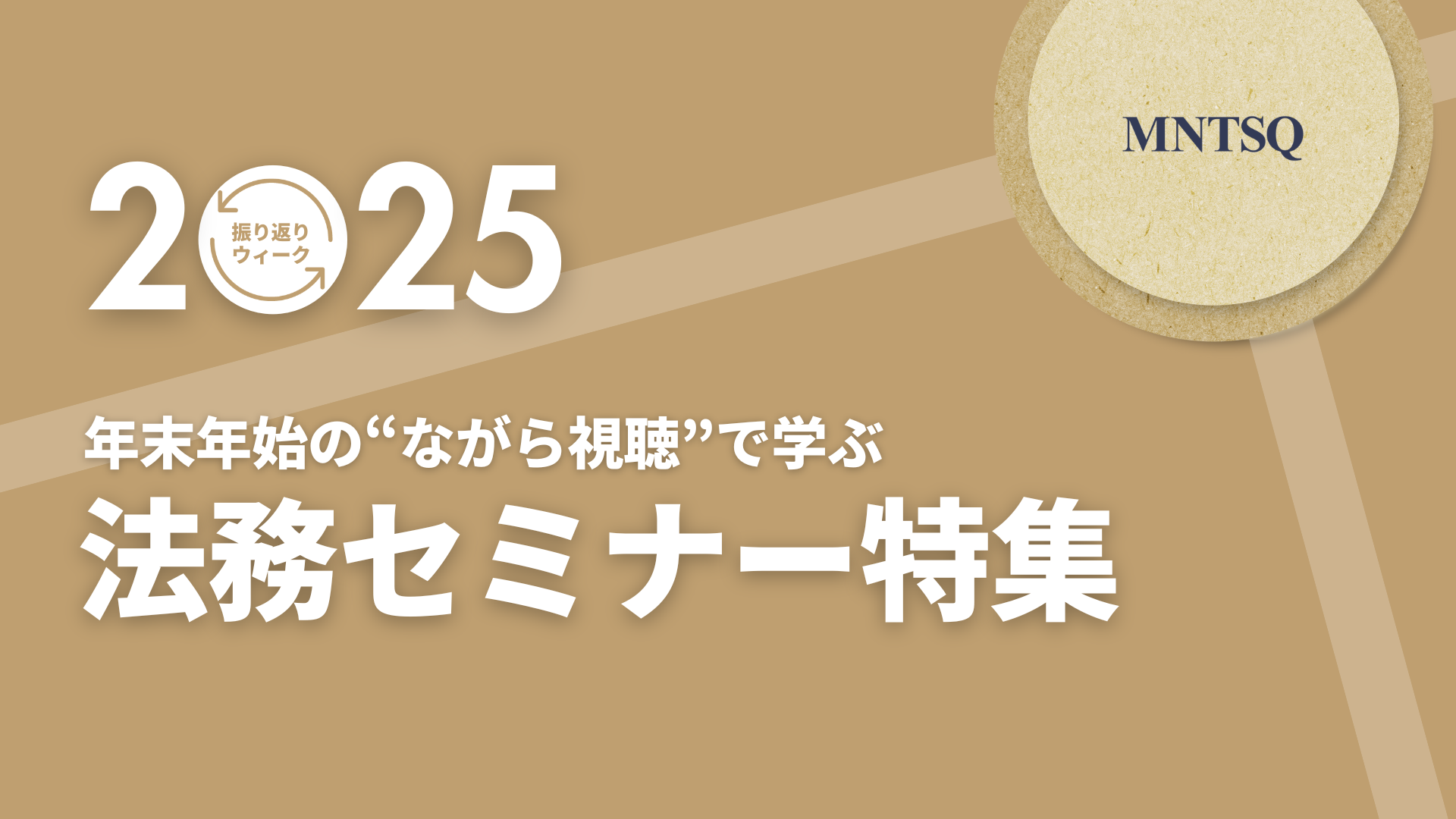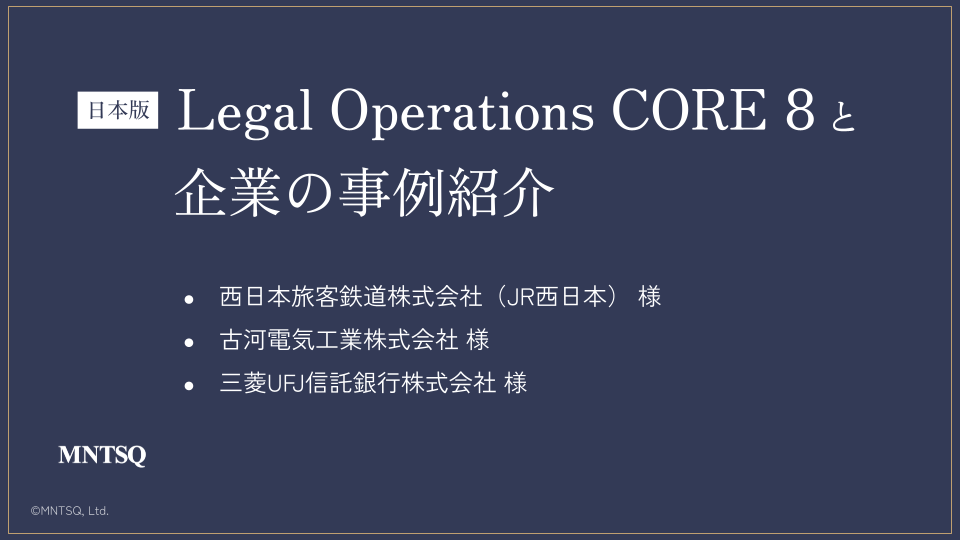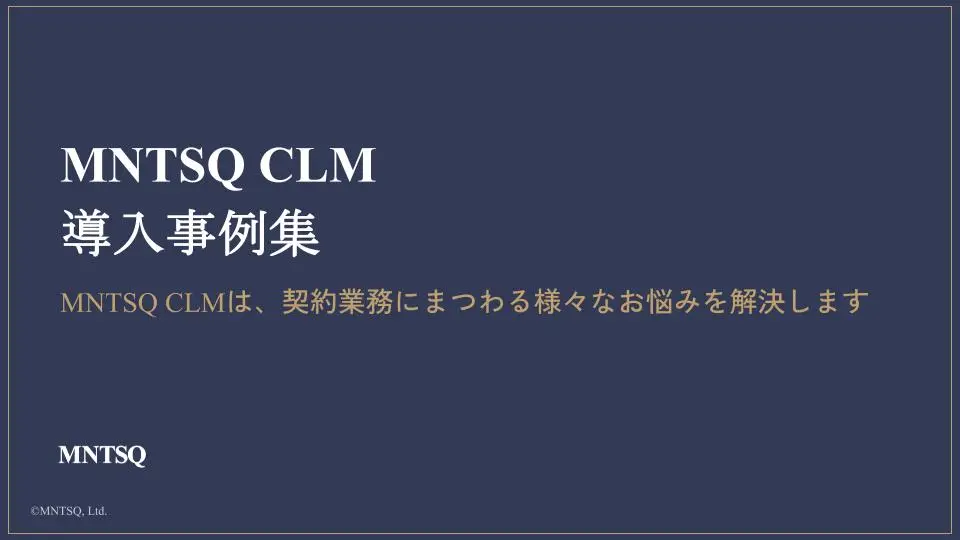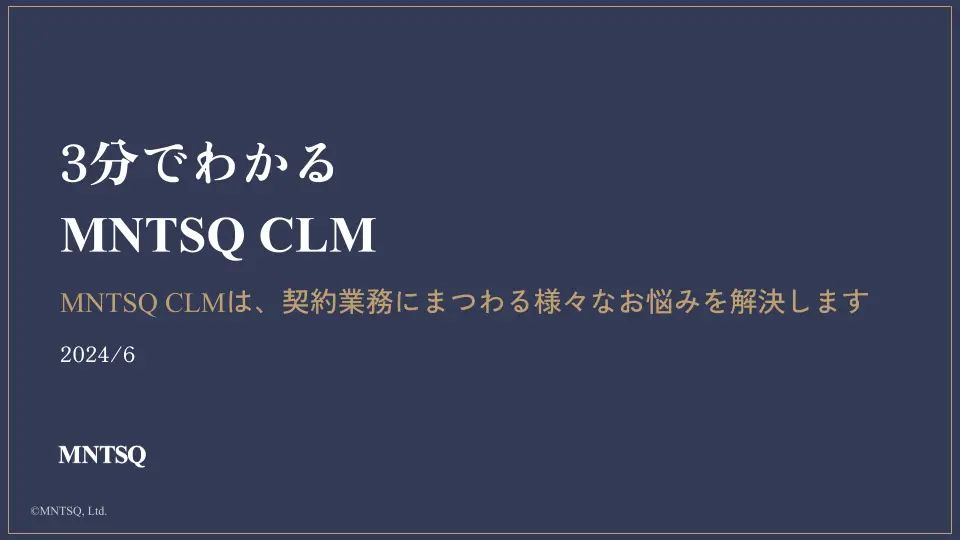予防法務とは?
予防法務は、企業が将来的に発生する可能性のある法的トラブルを未然に防ぐための取り組み全般を指す言葉です。契約書のチェック・社内規定の整備・リスクの洗い出しなどを行い、訴訟や紛争が起こる前にリスクを最小化する目的があります。
企業活動が複雑化する現代において、法務リスクを事前に把握し、対策を講じることは経営の安定性に直結します。予防法務は企業の法務部門のほか、専門の弁護士に依頼する形で取り組むのが一般的です。
戦略法務との違い
予防法務と戦略法務はどちらも法的リスクを事前に防止するための法務ですが、その目的には大きな違いがあります。予防法務は法的トラブルの回避が目的で、契約内容のチェックや社内体制の整備に重点を置きます。
一方、戦略法務は経営戦略の一環として法制度を活用し、M&Aや新規事業の展開の際に優位性を築くことを目的としています。
予防法務は守りの法務・戦略法務は攻めの法務ともいわれており、強固な法務体制の構築には、双方の法務活動をバランスよく展開することが必要不可欠です。
臨床法務との違い
臨床法務は、すでに発生した法的トラブルへの対応を目的とした法務業務です。たとえば、訴訟対応やクレーム処理、行政指導への対処などがこれにあたります。
臨床法務では、発生した事案の損害をいかに最小限にとどめられるかが求められます。臨床法務はトラブル発生後の有事の対応、予防法務はトラブル発生前の平時の対応という点で違いがあります。
予防法務の重要性
企業活動におけるさまざまな法的リスクを未然に防ぐ予防法務は、安定した企業活動を支える重要な取り組みといえます。
法的紛争が起こる前に回避できる
企業活動には常に法的リスクがともないますが、予防法務を徹底することでトラブルの発生を抑制できます。
たとえば、企業の法的トラブルのなかには、契約書内容の不備や社内規範の曖昧さが原因となるケースが少なくありません。予防法務ではこれらに潜んだリスクを見つけ出し、内容の改善やルールの整備を行うことで紛争の発生を未然に防いでいます。
法的紛争が起こった際の影響を最小限にできる
予防法務を行っても、法的トラブルのリスクを完全にゼロにすることはできません。しかし、トラブルが発生した際の損害を最小限に抑えることは可能です。
たとえば、契約書に適切な契約条項を設けたり社内規範を明確に定めたりしていれば、法廷で有利な証拠として扱われる可能性があります。また、トラブル発生時の対処法を整備していれば、緊急時に迅速かつ的確に対応でき、経営への影響を最小限に抑えられるでしょう。
社内のコンプライアンス体制を強化できる
予防法務は、社内のコンプライアンス体制の強化にも直結します。法令遵守を徹底するための社内規定や社内制度の整備によって、従業員一人ひとりの法的意識も高められるでしょう。
社内規定やチェック体制を構築することで、不正・違反行為の防止や早期発見も見込めます。また、社内コンプライアンス体制の強化は、ブランド価値や社会的信頼の向上にもつながります。
予防法務の具体的な内容
予防法務は、契約書や社内規定の整備など、日常業務のなかで実践されています。
契約書のリーガルチェック
契約書は、企業や個人と契約を結ぶ際に必要となる重要な文書です。予防法務では、契約締結前の契約書に潜むリスクや不利な条件を洗い出し、法的な観点から修正・改善を行うリーガルチェックを実施します。あらかじめ専門家の目で契約書内容を精査することで、将来的な紛争リスクを大幅に軽減できます。
社内規定の作成・リーガルチェック
企業内のルールである社内規定は、従業員の行動や業務の基準を定める重要な文書です。予防法務では、新たに規定を作成する場合や既存の規定を改定する際に、法令と照らし合わせて不備がないかを確認します。
事前のリーガルチェックを行うことで、労働法や個人情報保護法などの法令違反を未然に防ぎ、トラブルの発生を抑制できます。
知的財産権の取り扱いを定める
製品開発やマーケティング活動において、知的財産権の管理は極めて重要な項目です。予防法務では、著作権・商標権・特許権の適切な取得・管理・使用方法をルール化し、社内外のトラブルを未然に防ぐ対策を行います。
特にスタートアップや開発系の企業では、無用な訴訟リスクを回避するために、知的財産権に対する予防法務が有効といえます。
ハラスメント対策
職場におけるハラスメントは、企業の信頼を大きく損なうリスク要因となります。予防法務では、ハラスメントに関する社内規定の整備や研修の実施を通じて、あらゆるハラスメントの防止を図ります。
パワハラ・セクハラ・マタハラなどの定義を明確化し、相談窓口の設置や対応フローを規定することで、被害が発生した際の早期発見・適切な対応にもつながります。
労務系の法改正への対応
労働基準法や育児介護休業法など、労務関連法は定期的に改正されるため、企業はその都度柔軟に対応する必要があります。予防法務では、これらの法改正内容を正確に把握し、就業規則・労使協定・社内ルールなどの規定を速やかに見直すことが求められます。
法令違反は労基署からの指導や罰則の対象となるほか、従業員とのトラブルを引き起こす原因にもなります。事前に対応を行い、適切な運用体制を整えることが重要です。
新規事業の事前調査
新たなビジネスを始める際には、法的なリスクを洗い出す事前調査が必要不可欠です。対象業界の法規制・認可の必要性・契約上の制約事項などを確認し、事業推進にともなう法的課題を事前に明確にしましょう。
事業展開前に法的リスクを予防することで、行政指導や訴訟などのトラブルを事前に回避できます。特に医療や環境などの規制の厳しい業界では、事前調査が有効です。
株主総会の事前準備
株主総会は、企業経営における重要な意思決定の場であり、法律の遵守が求められます。予防法務では、開催通知の文面・議案の法的妥当性・議事録の整備など、株主総会の準備全般におけるリーガルチェックを行います。
事前に株主からの質問内容や想定されるトラブルにも備えることで、当日の混乱や訴訟リスクを防止できるでしょう。
顧問弁護士との連携
予防法務を効果的に機能させるためには、顧問弁護士と連携することが有効です。企業の法務部門だけでは判断が難しいケースでも、専門家の視点を取り入れることで法的リスクを早期に発見・対処できます。
契約書のリーガルチェック・法改正への対応・新規事業への助言などの幅広い場面で弁護士からアドバイスを受けることで、さまざまな法的リスクを最小化できます。
予防法務を依頼する弁護士を選ぶ際のチェックポイント
弁護士と提携して予防法務に取り組む場合は、信頼できる弁護士選びが欠かせません。以下のポイントをチェックし、自社に合った弁護士を見極めましょう。
依頼したい内容が対応範囲内か
ひとくちに弁護士といっても、人それぞれ得意分野が異なります。予防法務を中心に依頼する場合は、契約書のチェック・労務問題・知財の取り扱い・M&Aなどの予防法務領域に対応しているかを必ず確認しましょう。
専門外の弁護士と契約してしまうと助言が不十分になる可能性があるため、予防法務経験がある弁護士を採用することが重要です。
企業の予防法務を得意としているか
予防法務に特化した弁護士は、企業活動に伴うリスクを熟知しており、より的確なアドバイスを受けられます。企業の予防法務の経験が豊富な弁護士であれば、中長期的な契約の締結・法改正への対応・社内規定の改訂などの複雑な案件にもスムーズに対応できるでしょう。信頼できる弁護士を選定するために、過去の経験や実績をチェックすることが大切です。
専門知識をわかりやすく説明してくれるか
予防法務の取り組みを行う際は、素人には解釈が難しい法律用語が多用されるシーンが珍しくありません。そんなときに専門用語をわかりやすく丁寧に説明してくれる弁護士は、信頼できる弁護士といえるでしょう。
難解な法的リスクを素人向けに噛み砕いて伝えてもらえれば、社内担当者の理解力向上や社内ノウハウの蓄積にもつながります。
顧問料が適切か
予防法務は継続的な支援が必要なケースが多いため、顧問料の金額や契約内容が妥当かを確認することも重要です。顧問料の妥当性は、相談回数・対応内容・レスポンスの早さなどとのバランスを見て判断しましょう。
たとえ安価だとしても対応範囲が狭ければ効果が見込めないため、適切なアドバイスを得られる条件のもとで料金を比較することが大切です。
連絡の取りやすさ・レスポンスの早さに問題がないか
法的トラブルへの対応や契約に関する事柄など、企業における重要な判断の場面では、顧問弁護士の素早いレスポンスが必要不可欠です。
弁護士選びの際は、連絡への返信スピードや連絡手段の柔軟さなども必ずチェックしましょう。メール・電話・チャットアプリなどの複数のツールですぐに連絡を取れる状態にしておくと、有事の際にもすぐに対応してもらえるでしょう。
まとめ
予防法務は、企業活動における将来の法的トラブルを未然に防ぐために欠かせない取り組みです。安定した経営基盤を築くためにも、予防法務を徹底して経営リスクを最小限に抑えましょう。
MNTSQでは、法務領域の一連の業務プロセスを変革するサービスを提供しています。社内にある法務関連データを連携し、契約の作成・審査・管理からナレッジ化までを一気通貫でサポートすることで、リーガルリスクのマネジメントと法務業務の高速化を同時に実現します。興味のある担当者は、ぜひ以下からお問い合わせください。