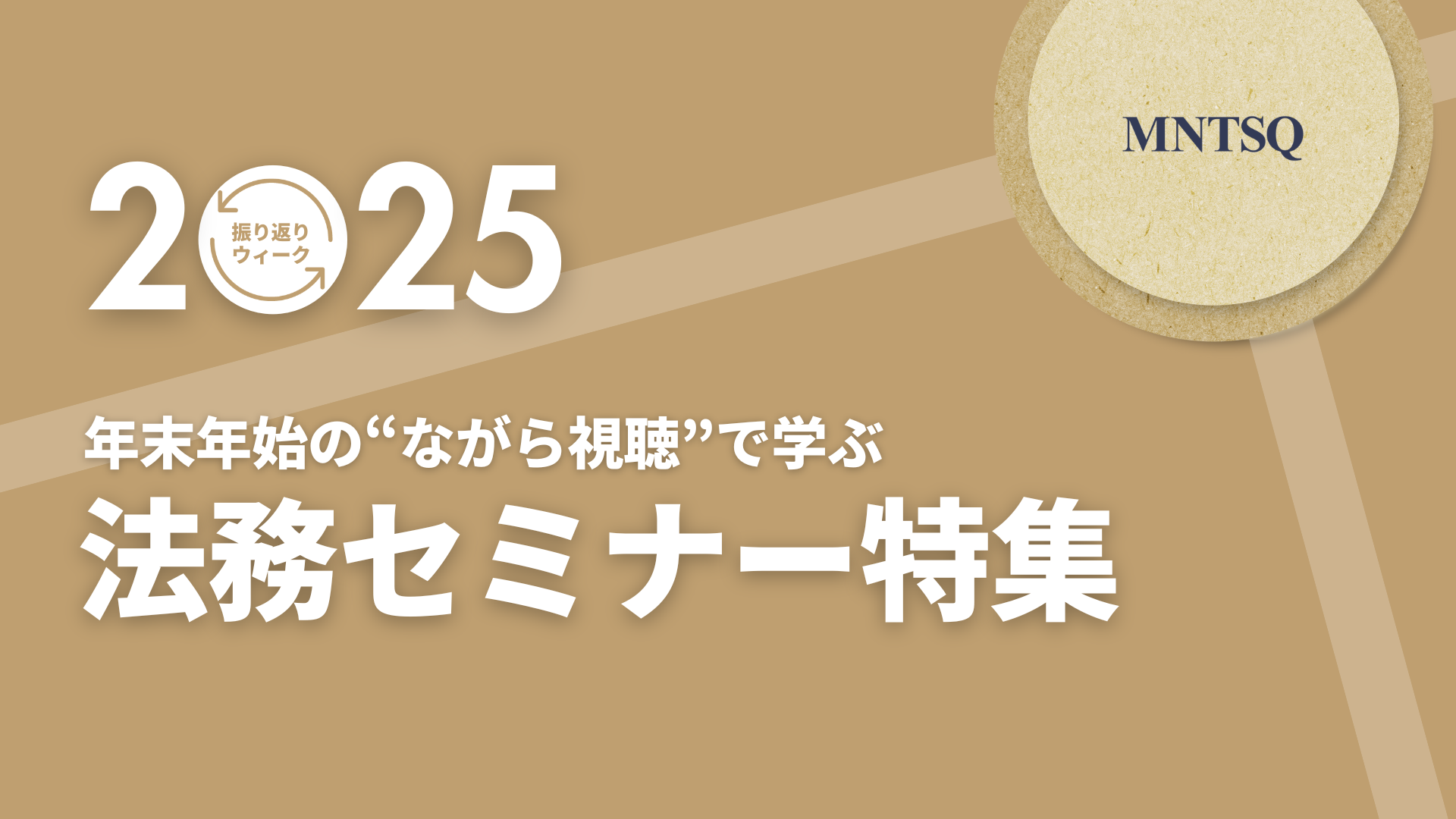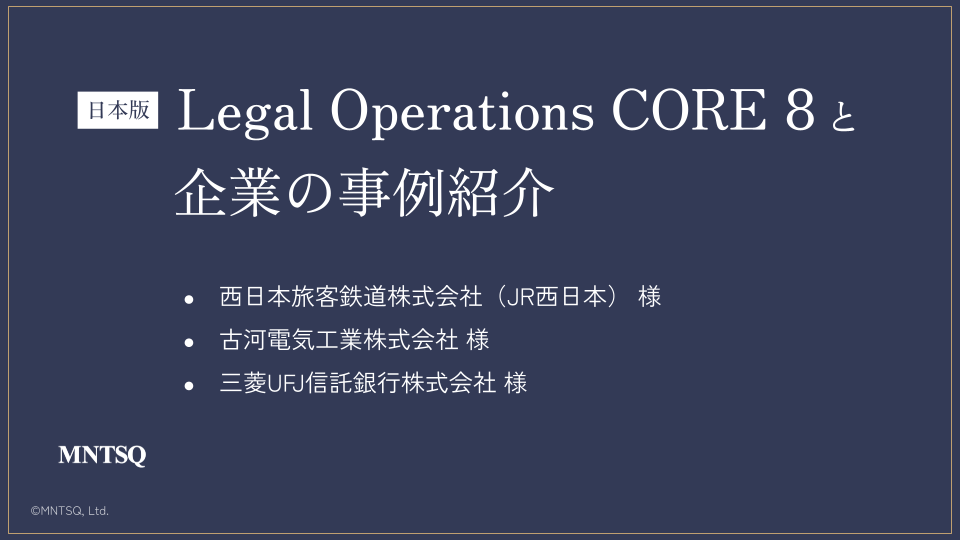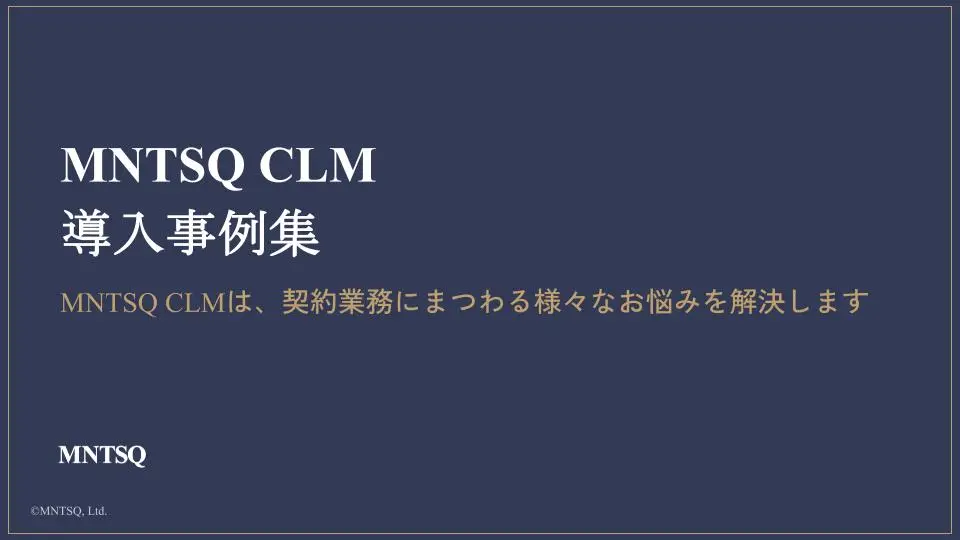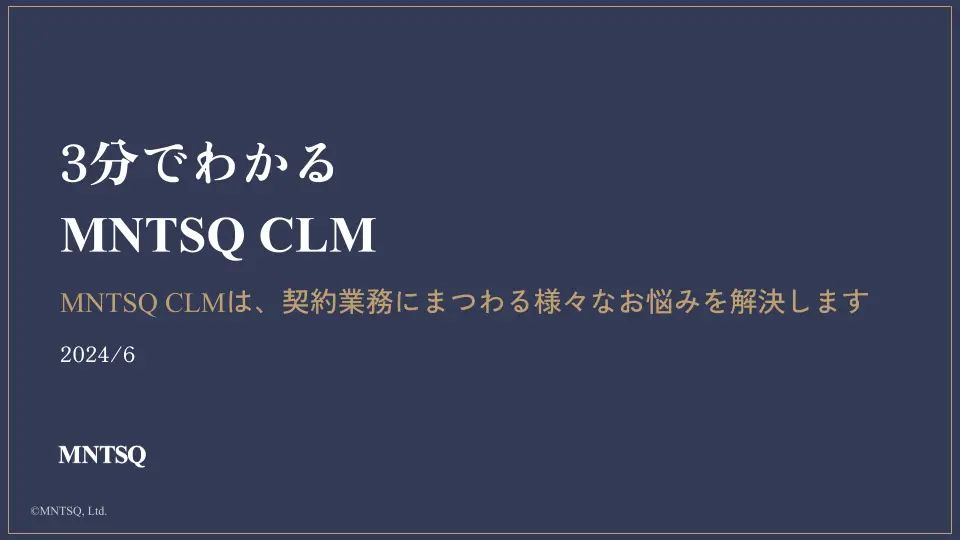<参加者>
総務本部知財法務部 部長 満木 秀彦様
知財法務部 金井 亜矢子様
知財法務部 関谷 千星様
MNTSQ カスタマーサクセス担当 田邉 崇宏
※以下、敬称略
※2025年5月時点の役職です
グローバル展開を強化:総務本部が担う法務業務の一元化
MNTSQ 田邉:
まずは貴社の法務部門の体制についてお聞かせください。

満木:
当社の法務部門はもともと、知財法務室という名称で取締役直轄の部署だったのですが、2024年に総務本部に組み込まれ、知財法務部という組織になりました。現在11名のメンバーが、契約書審査や法務相談といった業務に加え、安全保障輸出管理に関する輸出管理も担っています。法務は専任が1名、兼務が3名で、契約書審査のほか、顧問弁護士と連携して全社的な問い合わせ窓口としての役割も果たしています。
MNTSQ 田邉:
取締役直轄の組織から総務本部へと組織体制が変わったことで、どんなことが期待されているのでしょうか。
満木:
最も大きな目的としては、グループ会社の一体経営の実現です。近年では国内だけでなく海外のグループ会社も11か国で展開しており、売上の6〜7割を占めるほどになっています。
私たち本社の知財法務部としては、現在はグループ会社に対しては一部の契約書審査の対応にとどまり、その他の法務についてはグループ会社が直接海外の弁護士と連携して行っています。今後はそういった海外対応の法務についても、知財法務部で一元管理できるように体制づくりを進めているところです。会社の規模から見ても今ならまだ間に合うと考えています。
事業部とともに、ビジネス価値を高めていく法務部へ進化を目指す

MNTSQ 田邉:
日置電機様のカスタマーサクセス担当として、導入から運用まで伴走させていただいてきました。企業様がリーガルテックを導入する際、その目的は業務の効率化やナレッジマネジメントの強化などさまざまですが、日置電機様からは「社内での法務部のあり方を変えていきたい」という強い意思を、折に触れて感じてきました。その根底にある思いをお聞かせいただけますか。
満木:
私としては、「法務部をコストセンターからプロフィットセンターに変えたい」という強い思いがあります。一般的に法務部門というと、法務の専門的な知識をもとに、契約や法令に関する相談を受けて対応するのが主な役割になっていますが、相談に対して法令に基づいた簡単な回答だったら生成AIでも対応でき、ある程度の責任ある回答は、契約している弁護士さんに直接お任せしても問題はないわけです。
その中で、会社の内部にいる私たち「法務部門の人間が本当にやるべきことは何か」を考えると、「現場のビジネスに貢献できる法務」なのではないかと。事業部門と法令の専門家の間に立つ私たちが、ビジネスの目的や必要とされるスピード感に対する解像度が低く曖昧な立場で対応していては、弁護士側としても無難な回答しか出せず、それが障壁となって、本来獲得できたはずのビジネスチャンスを逃すことにもなりかねません。
MNTSQ 田邉:
確かに、法務レビューというと、法令に則ってイエスorノーの単純な回答になることも少なくないと思います。ビジネスを成功させる上での課題を抽出し、解決するための道筋を示すことにも、法務部門の力量が問われますよね。
満木:
その通りです。ビジネスの価値やプロセスを精緻に理解し、法令を遵守してビジネスを成功させるにはどうしたらいいか。ビジネスの価値を高める提案ができる法務部というのが、私たちが目指す姿です。
今期のテーマとしては、メンバー全員にプロアクティブに行動してもらうという目標を掲げ、業務の依頼を受け身で待つのではなく、積極的に事業の現場に関与し、ネットワークを広げて必要な情報をキャッチアップしていけるよう取り組んでもらっています。

MNTSQ 田邉:
法務部門のほうからの提案も含めて、事業部門と一緒にビジネスを練り上げていくスタイルを取られているのですね。
満木:
私たちのほうから現場のビジネスを理解する働きかけをすることで、事業部門からいつでも相談してもらえるような関係性を構築できれば理想的です。もちろん、私たち法務部門の姿勢だけでなく、会社全体の風土を変えていこうという試みですから、一朝一夕には達成できないことではありますが、まずはこちらから一歩踏み出そうと。
MNTSQ 田邉:
事業部門の皆さんとも一緒に協力して進めていく必要があると思いますが、事業部門とはどのようなコミュニケーションをとっているのでしょうか。
満木:
唐突に現場に法務の話を持ちかけても、事業部門としても戸惑ってしまいますよね。そこは各部長レベルの会議体で、私たち知財法務部として持っているリーガルリスクを説明し、会社全体の課題として共有する取り組みを進めています。部門を横断して意識を共有し、現場の変革を進めていく流れを作っていければと考えています。
DXの旗印は「脱メール・脱ハンコの徹底」
定着した慣習を疑い、変化を恐れない姿勢が変革を生む
MNTSQ 田邉:
私がこれまで担当してきた中でも、日置電機様はMNTSQを導入して非常に徹底したDXを実現されています。そのプロセスを含め、私自身も非常に勉強になりました。
満木:
法務部門のDXを推進するにあたり、まず宣言したのは「脱メール」です。経営層に「とにかくメールによる業務はダメです」と、きっぱり言いました(笑)。もちろん、事業部門から法務相談を受けること自体を避けたいわけではありません。
「〇〇さんお世話様です」「〇〇様お世話になっております」などの些細なことの積み重ねが無駄ですし、メールで法務相談を受けてしまうと属人化して情報が散逸して、ナレッジマネジメントが進まないという弊害もあります。MNTSQ導入まで、スクラッチ開発した契約管理システムを運用してきましたが、事業部門にとってはあまり使い勝手がよくなく、結局メールでの問い合わせは減りませんでした。それが、MNTSQ導入によって「脱メール」を完全に実現できたことは本当にありがたいです。
MNTSQ 田邉:
脱メールに加え、ペーパーレスの件もですよね。紙の契約書を含めて過去の契約書をすべて電子化してMNTSQにアーカイブする取り組みも、徹底されていると感じました。
満木:
「脱メール」と同時に実現したかったのが「脱ハンコ」です。きっかけは契約書ではありませんが、社内文書の押印欄にJPEG画像の印影が貼りつけられているケースが増え始め、デジタルの悪用が広がっていると感じました。押印の本来の意義を失って形骸化したハンコ文化もなくしたい古い慣習の一つです。

金井:
デジタル化の取り組みは、ナレッジマネジメントの強化の意味でも重要でした。前任者に都度聞いたり、メールやデータのフォルダ、紙の文書を時間をかけて探すような作業をしなくても、過去の案件に簡単にアクセスできるようになる状態が理想と考えてきました。
関谷:
MNTSQ内を検索すれば、例外なく過去の情報にアクセスできることを理想としていました。今はあちこち探し回るストレスなく、MNTSQでほしい情報を引き出せるようになったので、DXの意義をメンバーが実感する環境ができ始めているのではないかと思います。
MNTSQ 田邉:
DX推進の難しさには「定着した慣習の刷新」があると思います。責任が伴いますし、法務部門はもちろん、会社組織全体に浸透させる大変さもありますよね。
満木:
そうですね。私だけが声高に提唱しても、問題認識に共感して一緒に取り組んでくれるメンバーがいなければ実現できませんでした。
変化への原動力:多忙な中でも改革を推進する熱量の源泉

MNTSQ 田邉:
日々の業務に対応するだけでも多忙な中、課題があると感じていてもなかなか実行に移せないというケースも多い中で「動かしていこう」という、その熱量の源泉はどこにあるのでしょうか?
満木:
私自身、技術畑でキャリアを積んできて、その後3〜4年間社長直轄チームの経営戦略担当という立場で経営方針の浸透や事業プロセスの改善に取り組みました。この間に論理的思考力と、様々な社内業務をヒアリングして回った経験が、私を常に「なぜ?」と問う姿勢の基盤になっています。
当社は本社が地方にあり、首都圏の企業のように交流会や研修会で他社や他業界の方とコミュニケーションを取れる機会がなかなか得られませんが、幸い私は県外のセミナーや研修会、展示会などで外部と交流する機会に恵まれていました。いろんな話を聞き、長年引き継がれてきた会社のやり方も、良いものは踏襲し、目的がはっきりしないことや時代に合わない慣習は変えていくことが会社の成長にとっては必要だと確信し、自分ごととして捉えるようになっていきました。
その後、知財法務部の責任者に任命され、その自分の想いを折に触れてメンバーに伝えてきました。それにより、これまでの業務で違和感を抱く部分を変えていきたいと思っていたメンバーは、仮説検証的にでも改革をやってみようと活動し始めてくれました。
MNTSQ 田邉:
上意下達ではなく、メンバー一人ひとりが思いに共感して自律的に動いてこそ、改革は前に進んでいくのですね。メンバーとして金井さん、関谷さんはどのような想いを抱いているのでしょうか。
金井:
満木からは常々、法務部門が自社ビジネスに提供できる価値や、個人の業務が会社全体にどう貢献するかを俯瞰的に考えるようインプットされていました。頭では理解していたつもりでしたが、「今のままでは法務部門は必要ない」と危機感を強く感じたきっかけが2つあります。
1つ目は、海外事業が伸長する一方で、法務部門への依頼件数が横ばいだったことです。この数字から、自分たちの仕事が会社の成長に追いついておらず、新たな価値を生み出せていないと痛感しました。
2つ目は、外部の研修で他社の方と交流したことです。普段いかに社内の常識を基準に仕事をしているかを思い知らされました。
これら2つの出来事を機に、法務部門が会社にとって不可欠な存在になるための方法を深く考えるようになりました。それはまさに、部門の生き残りをかけた試みでした。こうした変化は、満木が真摯に伝え続けてくれた考えがあったからこそです。機能自体は大きく変わりませんが、目指すところを変えたことで、業務やアウトプットは確実に変化しています。

関谷:
個人的な考えですが、「“HIOKIの常識”は外の非常識かもしれない」と常に疑いながら仕事をしたいと思っています。満木の話にもあったように、外部を知ることが組織改善につながるという点に強く共感しています。
「これまでそうだったから」「自分たちが楽だから」といった理由で仕事はしたくありません。まずは一般的な法務プロセスを理解し、それをどうアレンジしてHIOKIに最適なものにするかを探求したい。それができて初めて、個人としても、法務部としても、真の価値が出せると考えています。
満木:
金井も関谷も、入社以降、日々の業務に携わる中で、それぞれ当事者意識を持って疑問をうやむやにせず、課題解決に取り組んできたメンバーでした。それが今の主体的な動きと成果に繋がったと思います。
「ツールを入れただけ」にしない:主体的な活用で実現する法務DX

MNTSQ 田邉:
日置電機様はMNTSQ導入にあたっても、従来の業務プロセスをどう見直し、MNTSQをどう活用するのか、DXで実現したいことのイメージを非常に明確に持っていらっしゃいましたよね。
関谷:
どんなに優れたツールを導入しても、現実の業務フローへどのように落とし込むかを自分たちで考え抜かなければ、その真価は発揮されないとプロジェクトを進める中で感じていました。ツールの活用が中途半端では、業務変革として意味がないと思っています。
満木:
田邉さんには、機能提案から進捗管理まで、当社に合わせてきめ細やかに伴走してもらえました。関谷が仕様やフローで迷い、私がフォローしきれない時も、田邉さんが様々な角度から的確な提案をくれたおかげで、課題を突き詰めて明確な解決策を見出すことができました。プロジェクトが進むにつれて安心感が増していき、本当に助かりました。
金井:
田邉さんに伴走しながら進めていただくなかでは、もう安心感しかありませんでしたね。

関谷:
毎回の定例会後には、定例で話したことも含めて情報共有していただいて、TODOや進捗管理などもしっかり握ってくださっていました。私だけで進めていたら、導入プロジェクトの進行は困難を極めていたと思います。
MNTSQ 田邉:
ありがとうございます。プロジェクトが順調に進んだのは、ひとえに日置電機様の明確なビジョンと改革への強い意思があってこそでした。私たちMNTSQは、サービスの成約をゴールではなくスタートと捉えています。
その先で、お客様と共にDXを推進し、システム活用による業務環境改善の道筋をサポートしていくのが私たちの役割です。今回、日置電機様とご一緒できたことは、私にとっても大変勉強になりました。今後も、法務部門の価値最大化に貢献できるよう、MNTSQとして全力で伴走してまいります。
本日は貴重なお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。