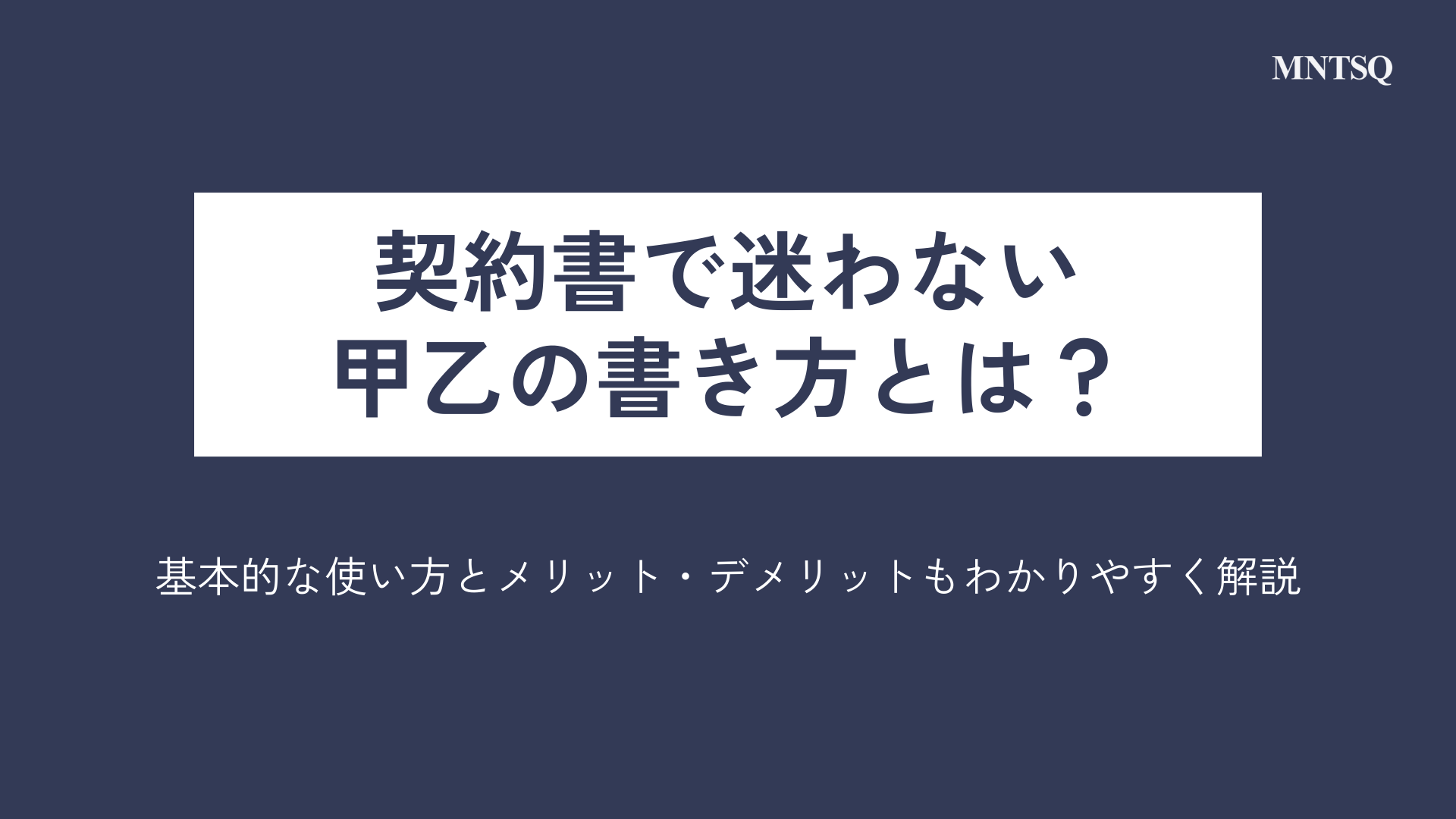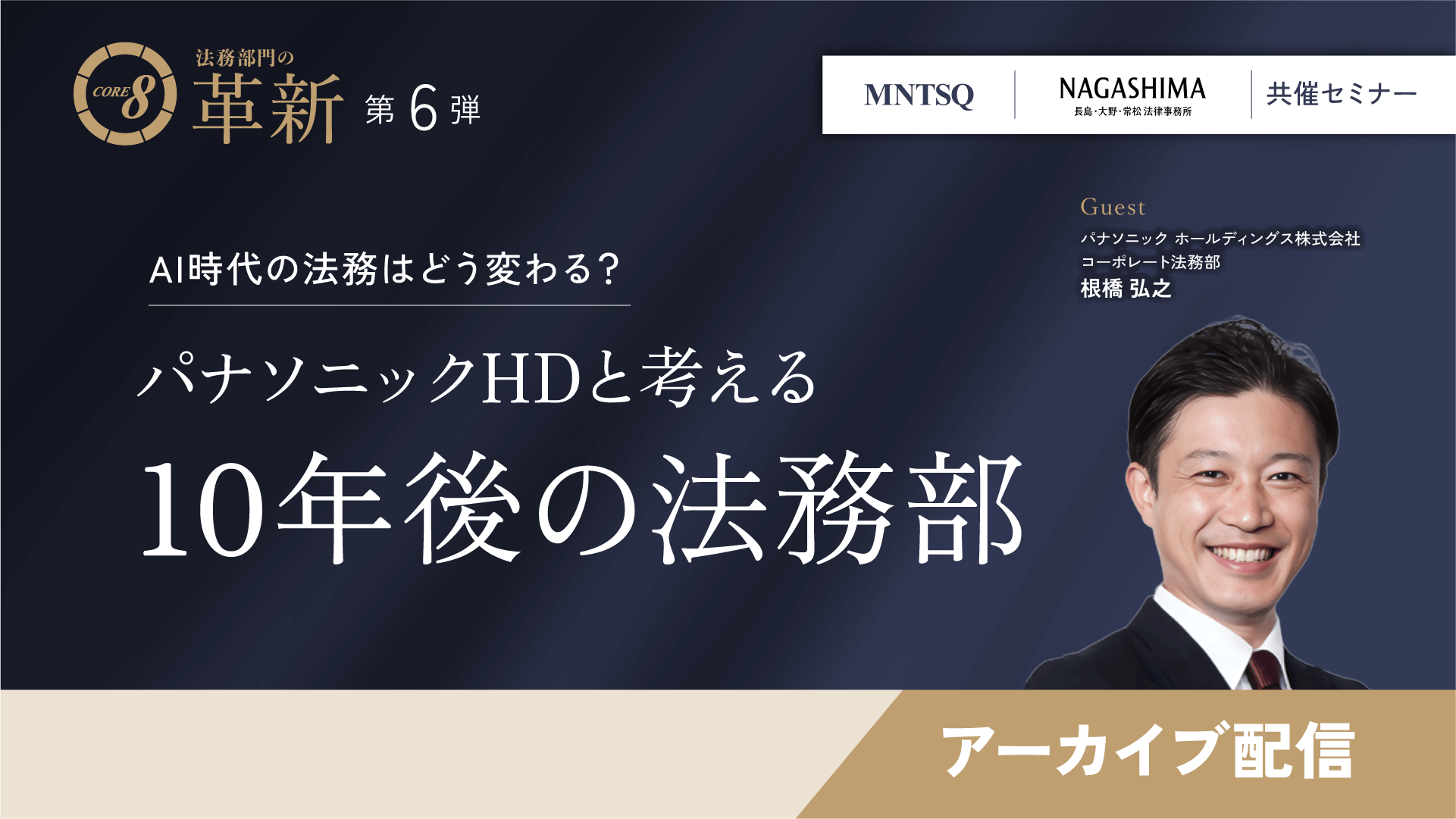契約書の甲乙とは?
契約書における「甲」「乙」とは、当事者を区別するための略称です。文書中で繰り返し正式名称を記載する手間を省き、記述を簡潔にする目的で使用されます。契約書の冒頭では「株式会社A(以下『甲』という)」のように定義し、その後の条文で「甲」「乙」として表現するのが一般的です。
契約書での甲乙の基本的な使い方
ここでは、甲乙表記の法律上の位置づけや慣習、三者以上の当事者への適用方法について詳しく解説します。
法律上の決まりはない
契約書において当事者をどのように表すかについて、法律による明文規定はありません。甲乙という表現は、単に文書の可読性を高めるための便宜的な手段に過ぎません。もっとも、商取引では慣習的にこの呼称が広く用いられており、取引先との文書整合性や読みやすさを確保する上でも、一般的な形式を押さえておくことが実務上の安心につながります。
慣習的には甲を上、乙を下にすることが多い
契約書で使われる甲と乙は当事者を区別するための記号であり、優劣はありません。ただし、「甲」「乙」「丙」「丁」「戊」と続く古来の十干の順で、甲が先に位置づけられる印象がああります。そのため、実務では契約の種類や慣例に応じて顧客や貸主や委託側を甲とする運用が選ばれる傾向があります。
とはいえ、どちらを甲とするかに明確な決まりはなく、企業や案件ごとに判断が異なります。双方が納得できる配置にすることが重要です。
三者以上の当事者でも使用可能
契約当事者が三者以上に及ぶ場合でも、甲乙の表記を拡張して用いることができます。その際は、古来の十干の順に「丙」「丁」「戊」などを加えていきます。たとえば三者間契約の場合、「甲・乙・丙」、四者間であれば「甲・乙・丙・丁」といった形で各社を識別します。
このように略称を体系的に付すことで、複数の当事者が関与する契約でも条文中の主語が明確になり、文書の整理性や可読性が高まります。
契約書の種類によって略称の使い方が異なる
契約の内容や目的によっては、「甲」「乙」以外の表記を採用することもあります。たとえば売買契約では「売主」「買主」、賃貸借契約では「貸主」「借主」、業務委託契約では「委託者」「受託者」といった形で、契約上の立場をそのまま略称とする方法です。
このような表記は、読み手が契約の構造を直感的に理解できるという利点があります。また、当事者の役割や義務を誤認しにくいため、契約文書の品質向上にもつながります。
甲乙表記のメリット
ここでは、甲乙表記を使用する具体的なメリットを詳しく解説します。
文章が短く、読みやすくなる
契約書で甲乙表記を使うことには、文章の簡潔化や読みやすさの向上といった明確な利点があります。特に正式名称が長い会社や団体の場合、繰り返し記載する手間を省き、条文をスッキリ整理できる点が大きなメリットです。
例えば、サンセット開発株式会社(以下「甲」という)とオーシャンデザイン株式会社(以下「乙」という)と定義した場合、条文中では「甲は本契約に基づき業務を遂行する」「乙はこれに同意する」といった形で簡潔に表現できます。
経験者が内容を把握しやすい
契約業務に慣れた人にとって、甲乙表記は自然で理解しやすいものです。法務担当者など、契約書を日常的に扱う人であれば、甲乙表記により条文の構造や関係性をより理解しやすくなります。文章が明瞭になることで、認識ミスのリスクを低減できるでしょう。
ひな形やテンプレートとして再利用できる
甲乙表記を使った契約書は、ひな形として他の契約にも応用できます。冒頭で甲乙を定義し直すだけで、別の契約書として再利用可能です。もちろん契約内容に応じた調整は必要ですが、作成作業の効率化には大きく役立ちます。
正式名称を何度も書く必要がない
正式名称を毎回書く必要がなくなるため、契約書全体が簡潔になるのもメリットです。特に複数ページにわたる契約書では、甲乙表記を使うことで条文の見通しが良くなり、受け取った側も理解しやすくなります。
甲乙表記のデメリット
一方で、甲乙表記は略称のため、一見するとわかりにくい表記です。以下で解説するデメリットを押さえ、混乱を招かないよう注意しましょう。
初めて見る人にはわかりにくい
略称だけでは、どの会社がどの役割か直感的にわかりにくい場合があります。特に条文が長く、義務や権利の内容が複雑な場合は混乱しやすいです。契約内容を双方が正しく把握できるようにするには、略称ではなく、企業名を短縮した表記や役割を明確にした呼称を採用することが有効なケースもあります。
主語を間違えると誤解が生じる
略称の誤用により、義務や権利の解釈が逆になることがあります。たとえば、情報保護の責任がある会社を誤って別の略称にしてしまうと、本来の責任範囲が曖昧になり、契約の効力や運用に支障をきたす場合があります。
三者以上の場合は混乱しやすい
契約当事者が三者以上になると、「甲・乙・丙・丁」と割り当てますが、どの記号がどの当事者を指すのか非常にわかりにくくなります。二者間なら「甲と乙が逆」というミスに気づきやすいものの、三者以上では記載ミスの発見が困難です。
社内ルールが統一されていないとミスが増える
社内で略称のルールが統一されていないと、作成者やレビュー担当者によって扱い方が異なる場合があります。その結果、条文の主語が不明確になったり、過去の契約書との整合性が取れなくなることがあります。標準化されたテンプレートやガイドラインを整備し、複数担当者によるダブルチェックを組み合わせることで、誤記や取り違えを防げます。
契約当事者を「甲」「乙」以外で表す場合
契約書において、当事者を「甲」「乙」以外の表記で示すことも可能です。主に以下の3つの方法があります。
当事者の略称で表す
契約書では、当事者の正式名称を毎回記載する代わりに、略称を定義して表記を簡潔にする方法もあります。たとえば、サンライズテクノロジーズ株式会社を「SR社」、ムーンライトソリューションズ株式会社を「ML社」と定めることで、以後の条文中では「SR社は〜する」「ML社は〜に同意する」といった形で整理できます。
このような略称を用いることで、文書全体の可読性が高まり、どの当事者を指すかを直感的に理解しやすくなります。ただし、契約ごとに略称を設定する必要があるため、汎用的な契約書のひな形として利用する場合は、都度修正や確認を行う手間が発生する点に留意が必要です。
契約上の立場で表す
契約書では、当事者を「甲・乙」ではなく、契約上の立場で表す方法も一般的です。たとえば売買契約であれば「売主・買主」、賃貸借契約であれば「貸主・借主」、業務委託契約であれば「委託者・受託者」といった具合です。
この表記方法は汎用性が高く、契約書のひな形にも適しています。また、条文中でどの当事者を指しているかが直感的に理解できるため、誤認や主語の取り違えを防ぐ効果もあります。
具体例:
・売買契約書:A株式会社(以下「売主」という)とB株式会社(以下「買主」という)
・金銭消費貸借契約書:C株式会社(以下「貸主」という)とD株式会社(以下「借主」という)
・業務委託契約書:E株式会社(以下「委託者」という)とF株式会社(以下「受託者」という)
このように、契約上の立場を明示することで、契約書を読む相手にとっても内容が分かりやすく、契約の正確性を高めることができます。
英文契約書での表記
英文契約書では、甲乙のような記号化は一般的ではありません。契約当事者は、固有名詞または契約上の立場で明確に示されます。
例:
・Sale and Purchase Agreement:This Agreement is entered into by [売主名称] (“Seller”) and [買主名称] (“Purchaser”).
・Lease Agreement:This Agreement is entered into by [賃貸人名称] (“Lessor”) and [賃借人名称] (“Lessee”).
・Outsourcing Agreement:This Agreement is entered into by [委託者名称] (“Entrustor”) and [受託者名称] (“Entrustee”).
契約上の立場を示す表記にすることで、契約書を読み慣れない相手にも内容を理解されやすくなります。
甲乙表記のミスを防ぐ方法3選
甲乙表記を使用する場合、誤記や取り違えによるトラブルを防止するための方法として、以下の3点が有効です。
甲乙以外の表記を活用する
当事者を略称や契約上の立場で示すと、誰がどの義務や権利を持つかが明確になり、誤解や取り違えを防げます。たとえば「売主」と「買主」と表記するだけで、条文を読みやすくできます。
複数担当者でダブルチェックを行う
作成後は複数の担当者で内容をチェックし、表記の取り違えや誤記を早期に発見します。また、レビュー支援ツールを使うと、複雑な案件や関係者が多い場合でも精度を上げられます。
標準化されたテンプレートを使用する
標準化されたひな形を使うことで、表記の不統一や作業ミスを減らせます。契約の種類ごとにテンプレートを用意し、冒頭で略称や役割を定義しておくと、効率的かつ正確に文書を作成できるでしょう。
まとめ
本記事では、契約書における甲乙表記の基本やメリット・デメリット、甲乙以外の表記方法やミス防止策を解説しました。甲乙を用いることで条文が整理され、長い会社名を繰り返す手間を省き、読みやすさも向上します。
ただし、初めて契約書を見る人や複数の当事者が関わる場合は混乱することもあります。そのため、社内ルールの統一や標準化テンプレート、複数担当者によるチェック体制が重要です。作成の効率化と正確性を高めるには、導入実績のある契約書作成をワンストップで支援できるツールの活用も有効です。詳細は以下よりご確認ください。